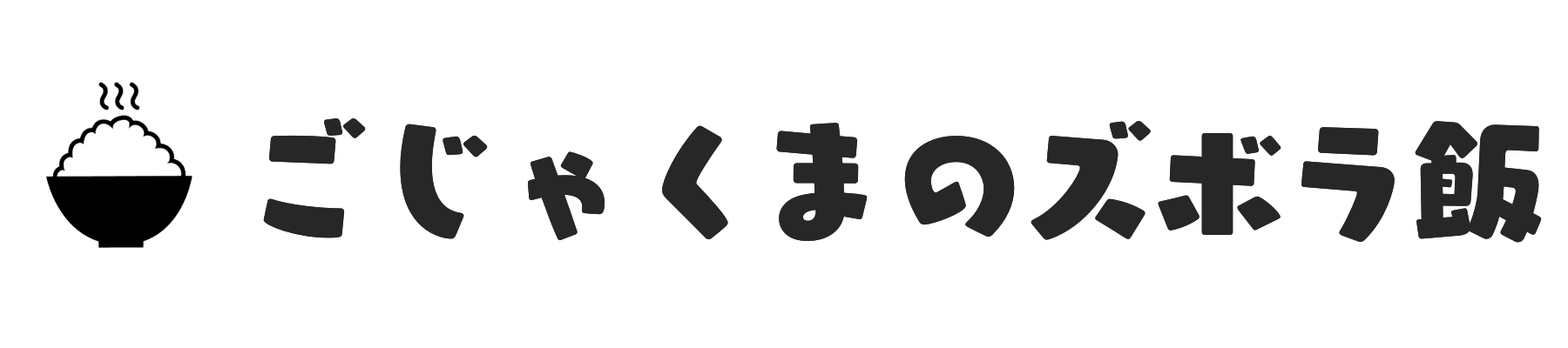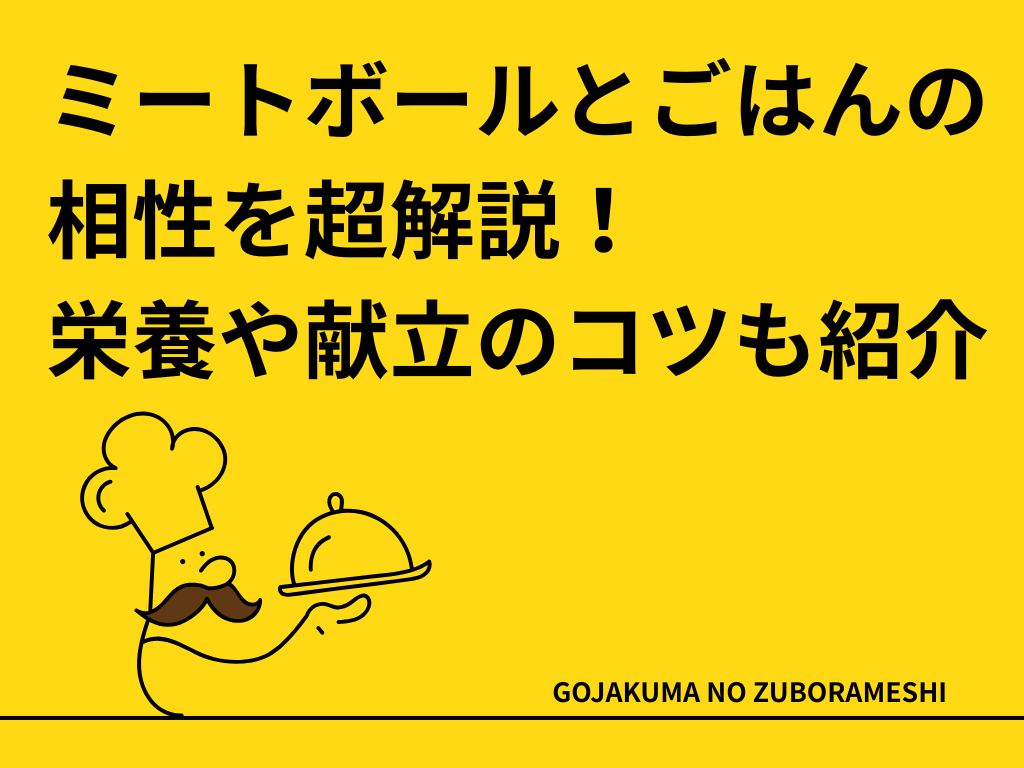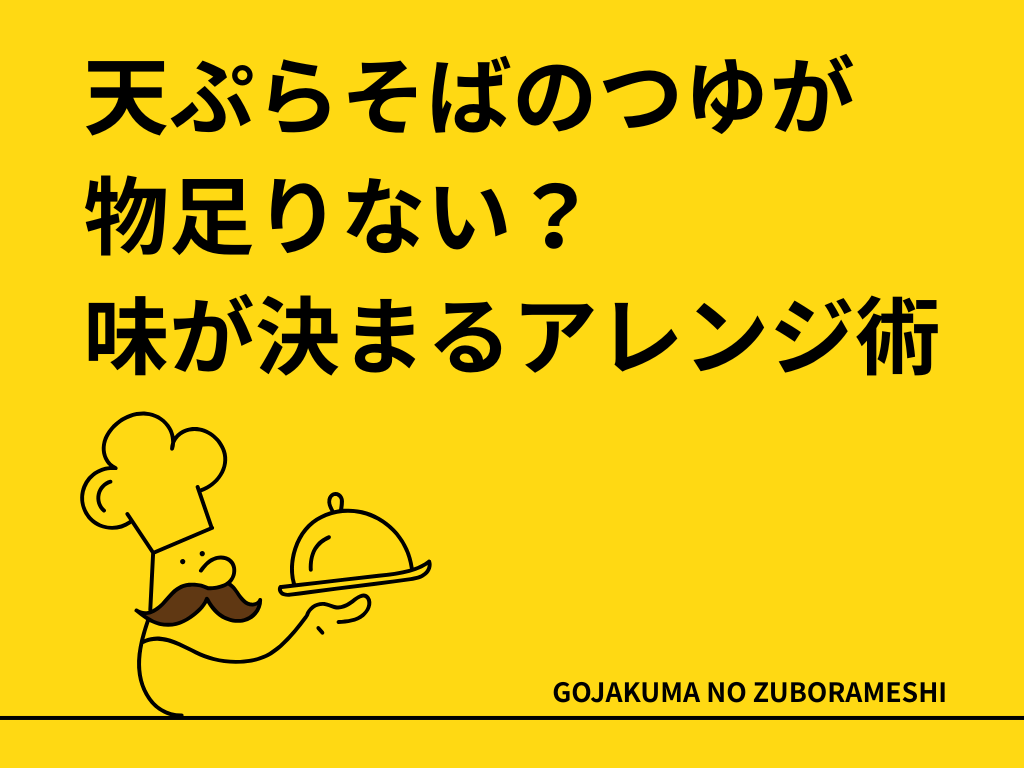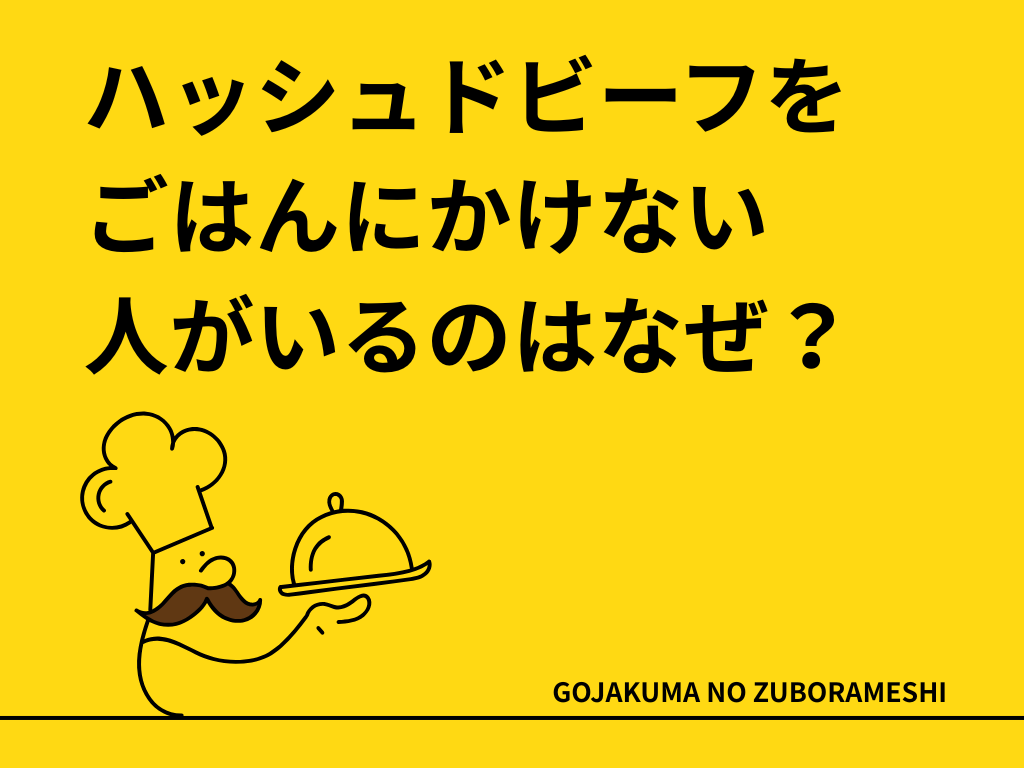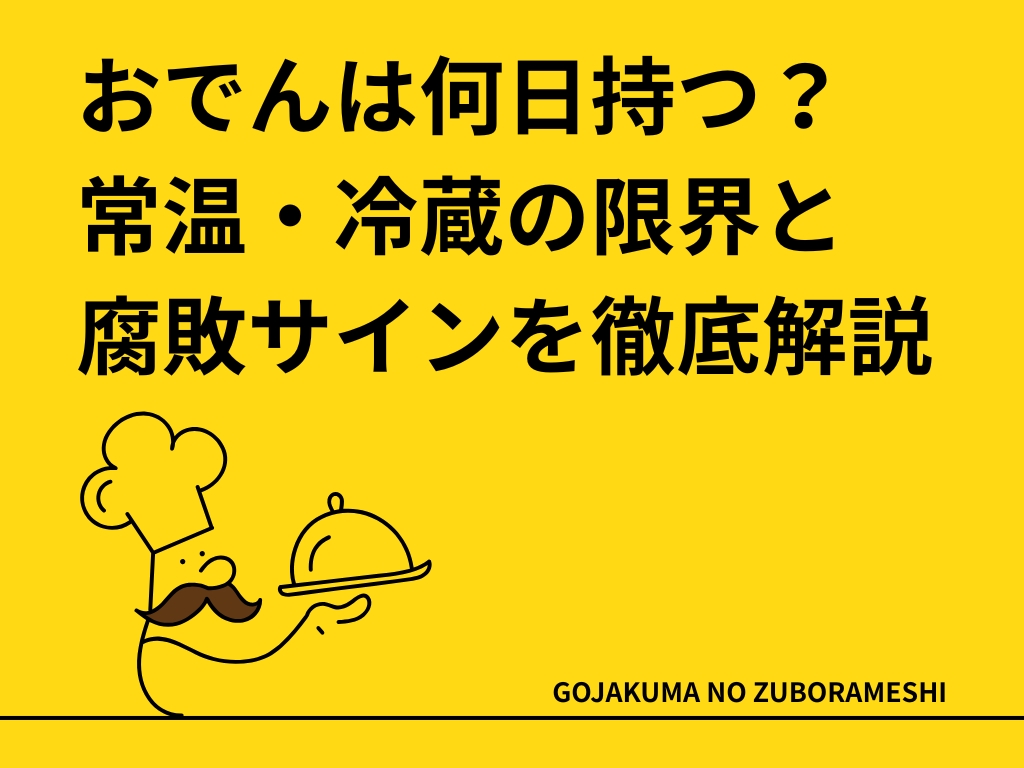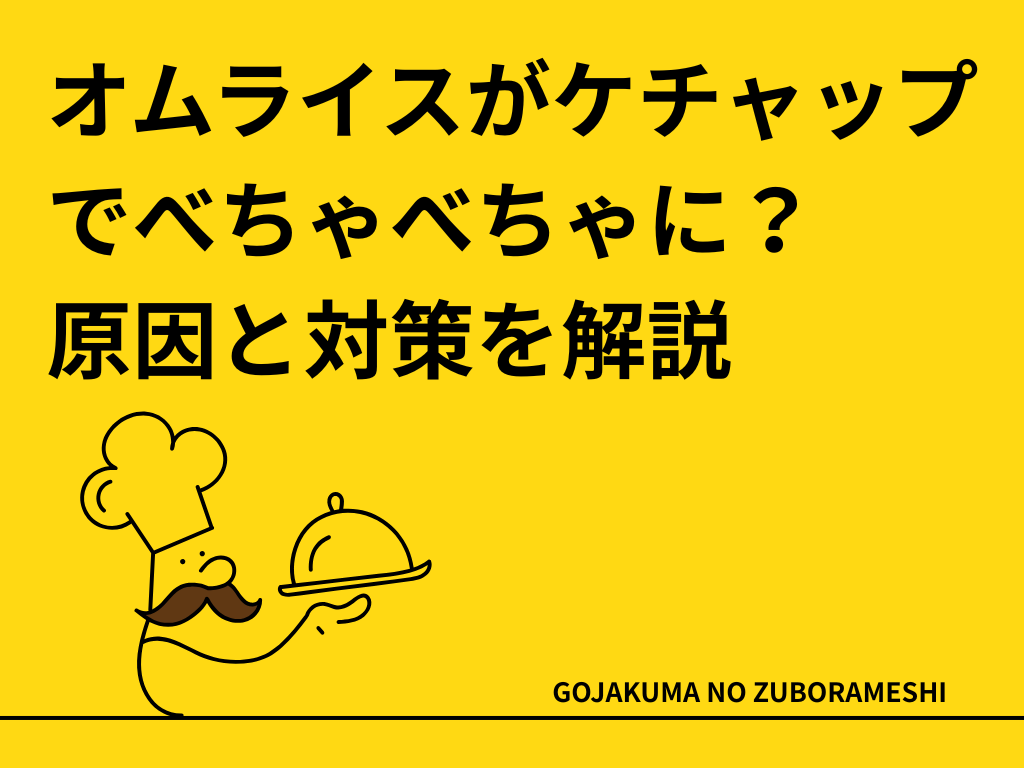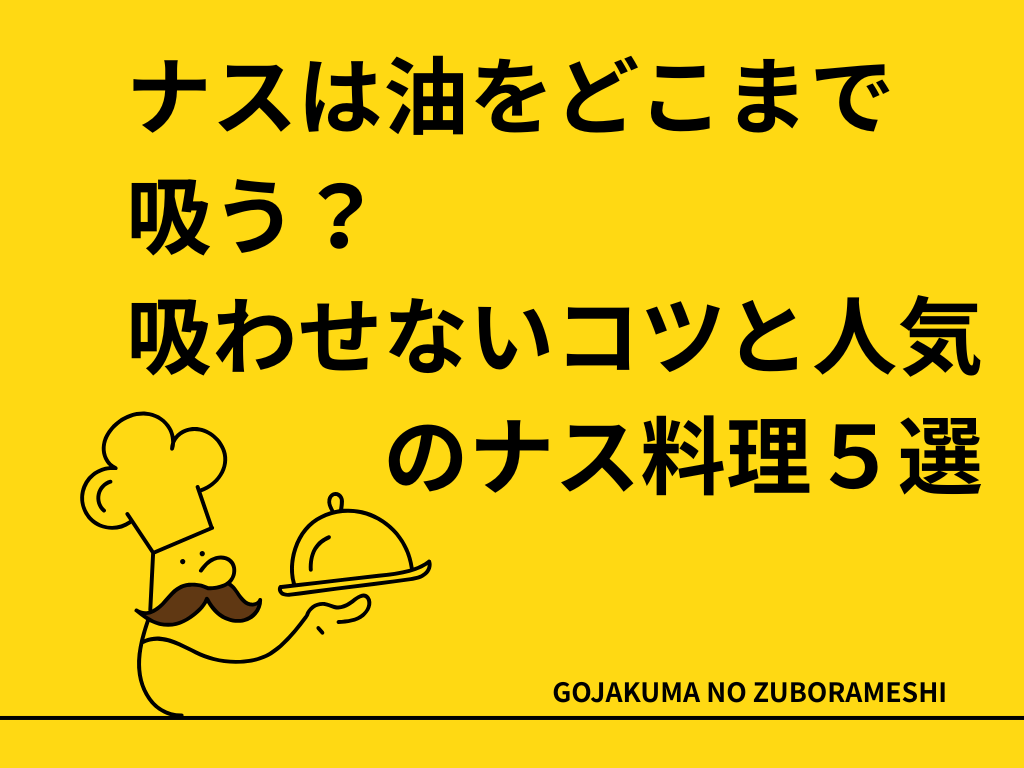もつ鍋のもつが臭い原因とは?簡単・確実な臭み消し術
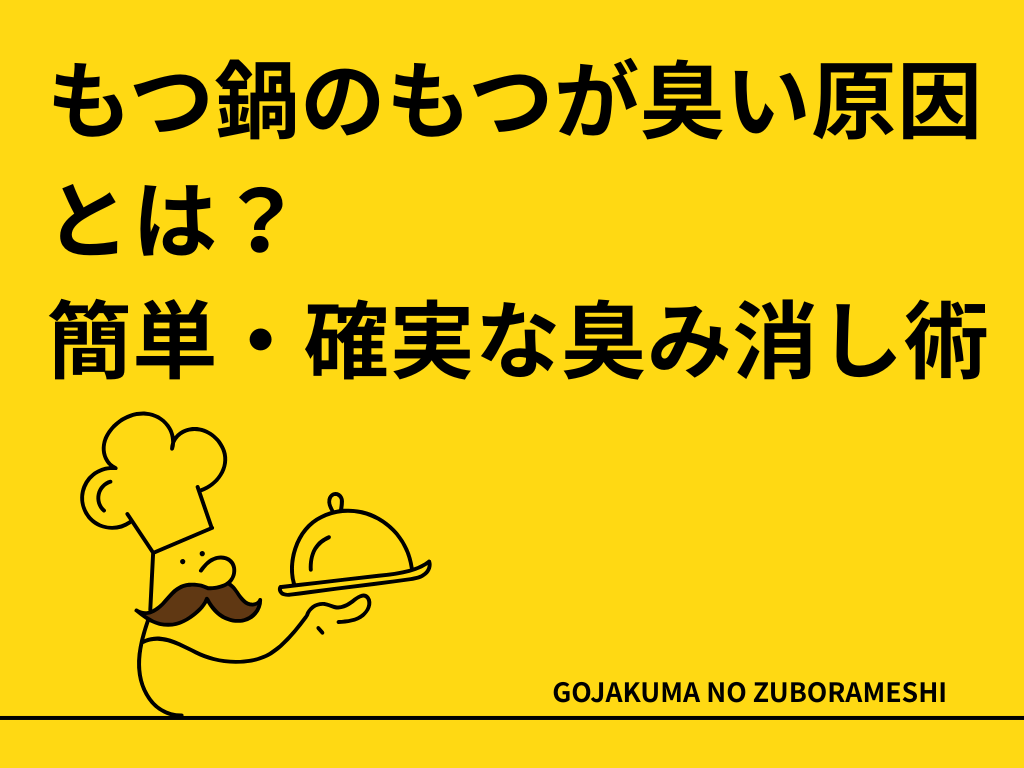
自宅で美味しいもつ鍋を作ろうとしたのに、もつが臭くて失敗し、後悔した経験はありませんか。もつ鍋のもつが臭いと感じる原因は、実にさまざまです。
例えば、使用するもつの部位、あるいは牛か豚かといった種類の違い、日持ちや鮮度の問題が考えられます。
そして何より、臭いを左右するのが下処理の方法です。適切な臭いの消し方を知らないと、せっかくの料理が台無しになってしまいます。
この記事では、もつ鍋が臭くなる根本的な原因から、家庭でできるプロ並みの下処理テクニック、臭みを旨味に変える美味しいスープの作り方、風味を豊かにするにんにくの上手な使い方、さらには食後の気になる口臭対策まで、あなたの悩みを総合的に解決する情報を詳しく解説していきます。
- もつが臭くなる根本的な原因
- 家庭でできるプロ並みの下処理方法
- 臭みを消して旨味を引き出す調理のコツ
- 食後の気になる悩みまでの解消法
もつ鍋のもつが臭い主な原因を解説
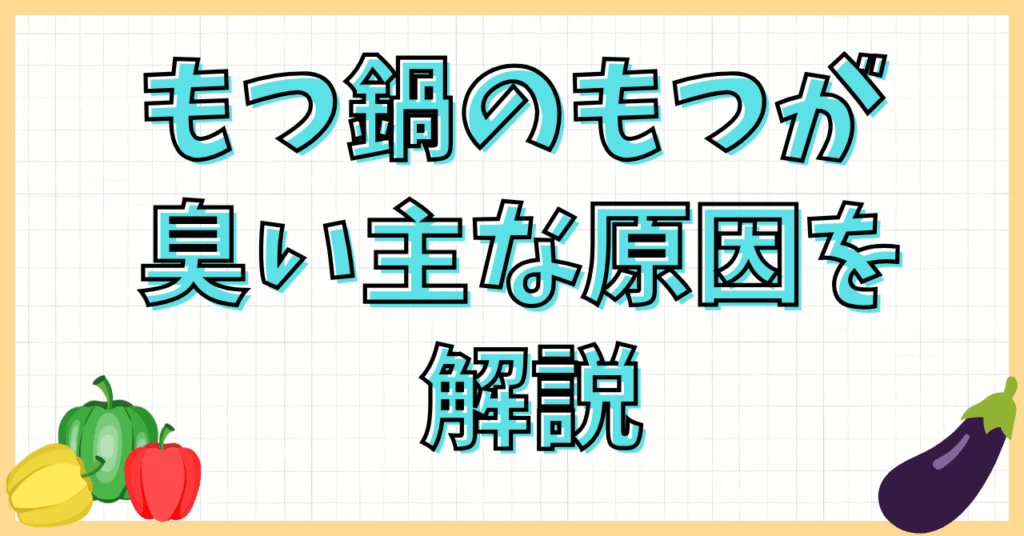
- 牛か豚か、もつの種類で臭いは違う
- 臭みの強さはもつの部位で決まる
- もつの日持ちと鮮度が臭いに影響
- 臭いの原因は不十分な下処理かも
牛か豚か、もつの種類で臭いは違う
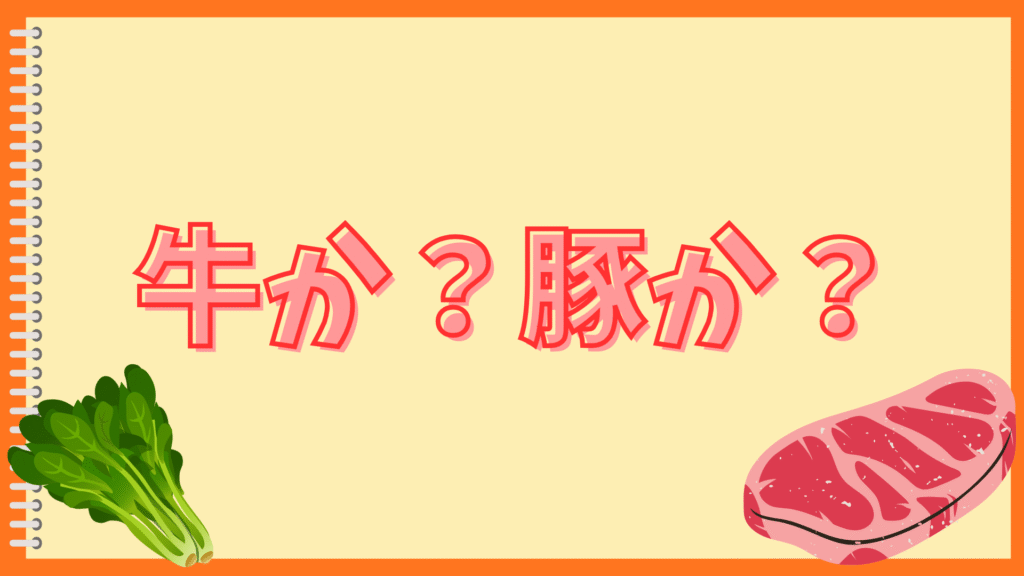
もつ鍋の主役であるもつですが、牛と豚のどちらを使うかによって、風味や臭いの強さが大きく変わってきます。
一般的に、本格的なもつ鍋店で提供されるのは牛もつが多く、豚もつに比べて臭みが少ないとされています。
なぜなら、牛と豚では食性や消化器官の構造が異なるため、内臓に残る匂いにも違いが生まれるからです。
豚もつは牛もつよりも比較的安価でスーパーなどでも手に入りやすいですが、特有の臭いが強い傾向にあります。
そのため、家庭で調理する際は、より丁寧な下処理が求められることになります。
もちろん、豚もつにも独特の旨味がありますが、もつ鍋初心者の方や、臭いをできるだけ避けたい方は、牛もつを選ぶのが無難な選択と言えます。
近くの店舗で牛もつが手に入らない場合は、インターネット通販を利用すれば、高品質な国産牛もつを購入することも可能です。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 牛もつ | 脂に甘みとコクがあり、柔らかい。豚に比べて臭みが少ない。 | 本格的な味わいが楽しめる。比較的扱いやすい。 | 豚もつより価格が高い傾向にある。 |
| 豚もつ | あっさりとした旨味がある。牛に比べて臭みが強い傾向。 | 比較的安価で手に入りやすい。 | 臭みを取るために、より丁寧な下処理が必要。 |
臭みの強さはもつの部位で決まる
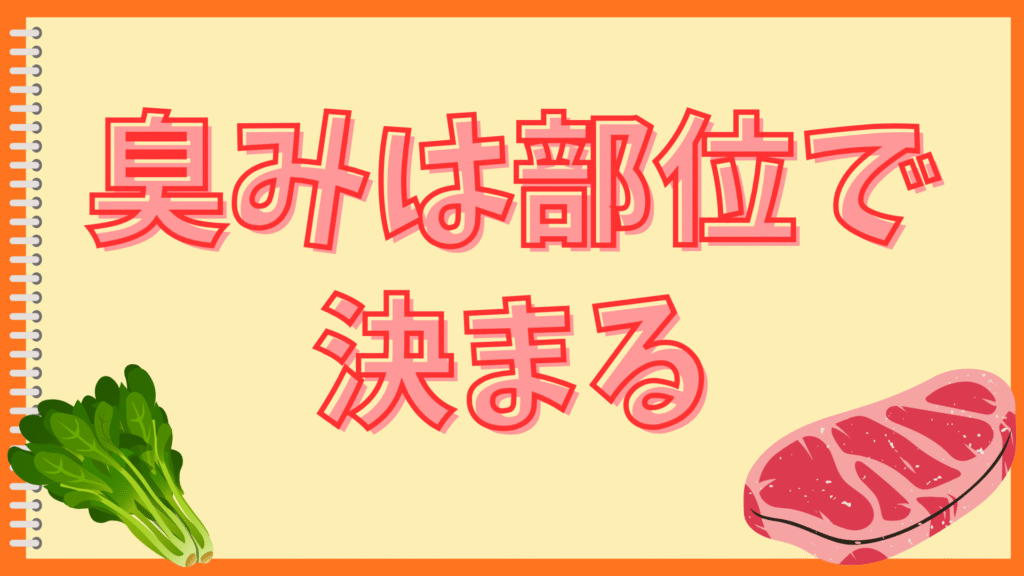
「もつ」と一括りに言っても、牛や豚の内臓にはさまざまな部位が存在し、それぞれ食感や風味、そして臭いの強さが全く異なります。
もつ鍋の味わいは、どの部位を選ぶかによって大きく左右されるため、それぞれの特徴を理解しておくことが、美味しいもつ鍋作りの第一歩となります。
もつは大きく分けて、消化物を処理する役割を持つ小腸や大腸などの「白もつ」と、心臓(ハツ)や胃(ミノ、センマイなど)といった「赤もつ」に分類できます。
一般的に、もつ鍋でよく使われるのは、ぷりぷりとした食感と脂の甘みが魅力の「白もつ」です。
もつ鍋の定番部位
- 小腸(マルチョウ、コプチャン)もつ鍋の王道とも言える部位です。筒状の形状で、内側にたっぷりと良質な脂を蓄えています。この脂がスープに溶け出すことで、濃厚なコクと甘みが生まれます。食感は非常に柔らかく、とろけるような口当たりが特徴です。
- 大腸(シマチョウ、テッチャン)小腸よりも厚みがあり、表面のしま模様が特徴的な部位です。小腸に比べると脂は少なめですが、その分、しっかりとした歯ごたえと弾力を楽しめます。噛むほどに旨味が広がるため、食感を重視する方におすすめです。
その他の部位
ミックスもつとして販売されている商品には、以下のような部位が含まれていることもあります。これらは比較的臭みが少ないため、良いアクセントになります。
| 部位 | 主な特徴 | 臭いの強さ |
| センマイ(第三胃) | 無数のヒダがあり、独特のコリコリとした食感。脂がほとんどなく淡白。 | 少ない |
| ギアラ(第四胃) | 赤センマイとも呼ばれる。適度な脂と歯ごたえのバランスが良い。 | やや少ない |
| ハツ(心臓) | 臭みがほとんどなく、赤身肉に近い旨味。サクサクとした食感。 | 非常に少ない |
スーパーで手軽に購入できるミックスホルモンは、さまざまな部位の味や食感を楽しめる一方で、臭いの強い部位が含まれている可能性もあります。
どの部位が入っているか確認し、丁寧な下処理を心がけることが大切です。
もつの日持ちと鮮度が臭いに影響
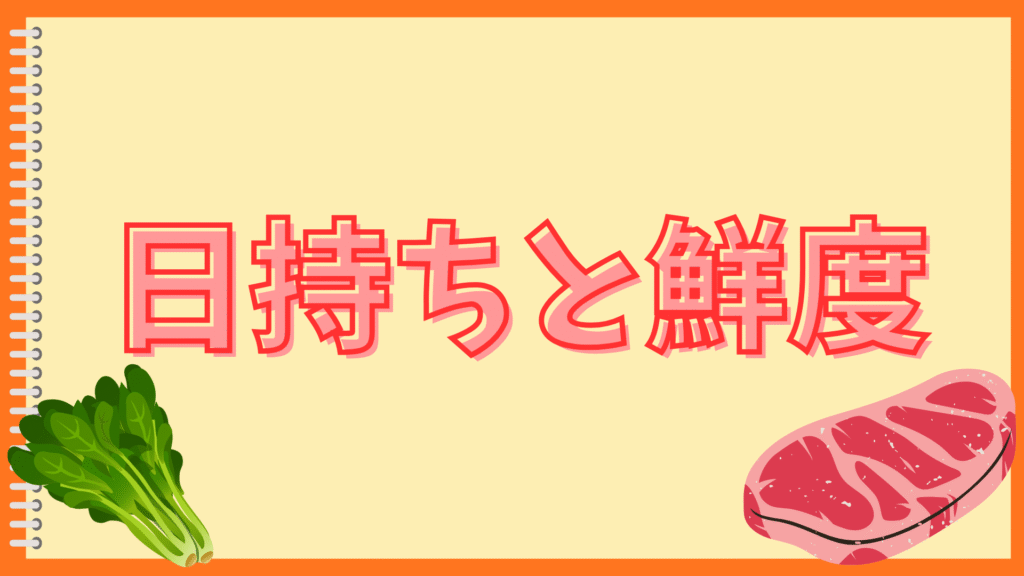
もつ鍋の美味しさを左右する上で、下処理と同じくらい大切なのが、もつの「鮮度」です。←これマジで大事!!
もつは精肉に比べて非常に傷みやすい食材であり、鮮度が落ちると、あっという間に不快な臭いが発生してしまいます。
内臓肉は、筋肉の部分である精肉と比べて水分や血液を多く含んでおり、微生物が繁殖しやすい環境にあります。
そのため、購入後は時間との勝負になります。たとえ消費期限内であっても、購入した翌日にはもう臭みが出始めている、ということも珍しくありません。
鮮度の見分け方と保存の目安
新鮮なもつは、全体的にピンク色でハリとツヤがあります。逆に、色がくすんでいたり、ドリップ(肉汁)がたくさん出ていたりするものは、鮮度が落ち始めているサインです。
冷蔵庫で保存する場合、購入してから1〜2日以内には調理するのが理想です。もしすぐに使わないのであれば、後述する下処理を済ませてから、小分けにして冷凍保存することをおすすめします。
冷凍すれば2週間〜1ヶ月程度は保存が可能ですが、それでも早めに使い切るに越したことはありません。
腐敗したもつの危険性
鮮度がさらに落ちて腐敗が始まると、アンモニア臭や酸っぱい匂いなど、明らかに異常な悪臭がします。
また、色が黒っぽく変色したり、表面がぬるぬるとしたりするのも危険な兆候です。
このような状態のもつは、下処理をしても臭みを取り除くことはできず、食べると食中毒を引き起こす危険性が非常に高いため、絶対に食べずに処分してください。
臭いの原因は不十分な下処理かも
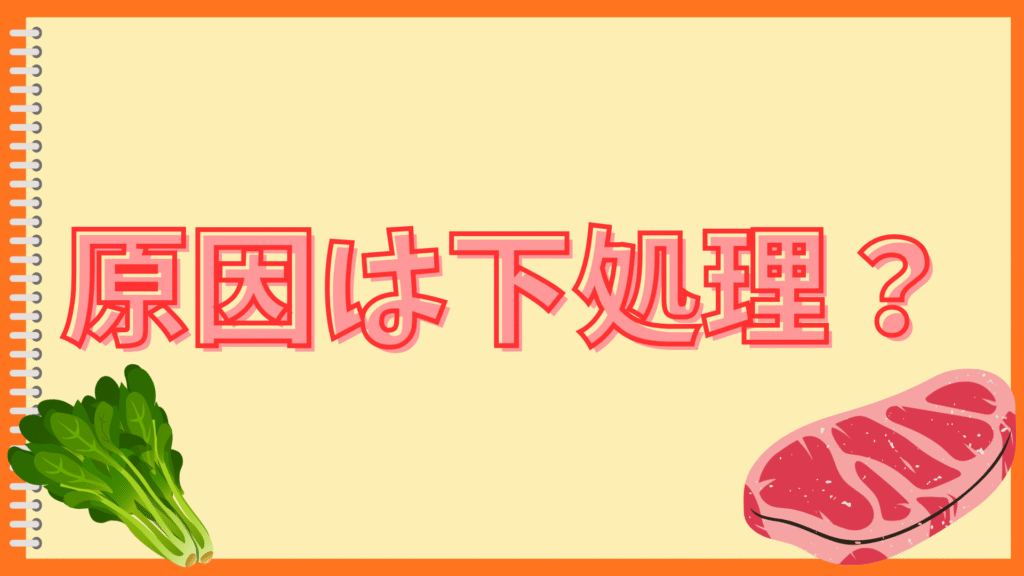
家庭でもつ鍋を作った際に「お店のような味にならない」「どうしてもうまくいかない」と感じる最大の原因は、この「下処理」が不十分であるケースがほとんどです。
もつは内臓であるため、消化途中の内容物による汚れや独特のぬめり、そして過剰な脂が付着しています。
これらが臭みの直接的な原因となります。
この下処理を丁寧に行うことで、不快な臭いだけを取り除き、もつ本来が持つ豊かな旨味とコクだけを残すことができます。
スーパーなどで「ボイル済み」「下処理済み」と表示されているもつを見かけることがあります。これらは一見すると、そのまま使えそうに思えるかもしれません。
しかし、加工されてから時間が経過している場合が多く、パックの中で再び臭みが発生している可能性があります。
そのため、たとえボイル済みのものであっても、家庭で調理する前にもう一度、これから紹介する下処理を行うことを強く推奨します。この一手間を加えるか加えないかで、もつ鍋の仕上がりは劇的に変わります。
面倒に感じるかもしれませんが、美味しいもつ鍋を味わうための最も大切な工程だと考えて、丁寧に取り組みましょう。
もつ鍋のもつが臭い時の対処法まとめ
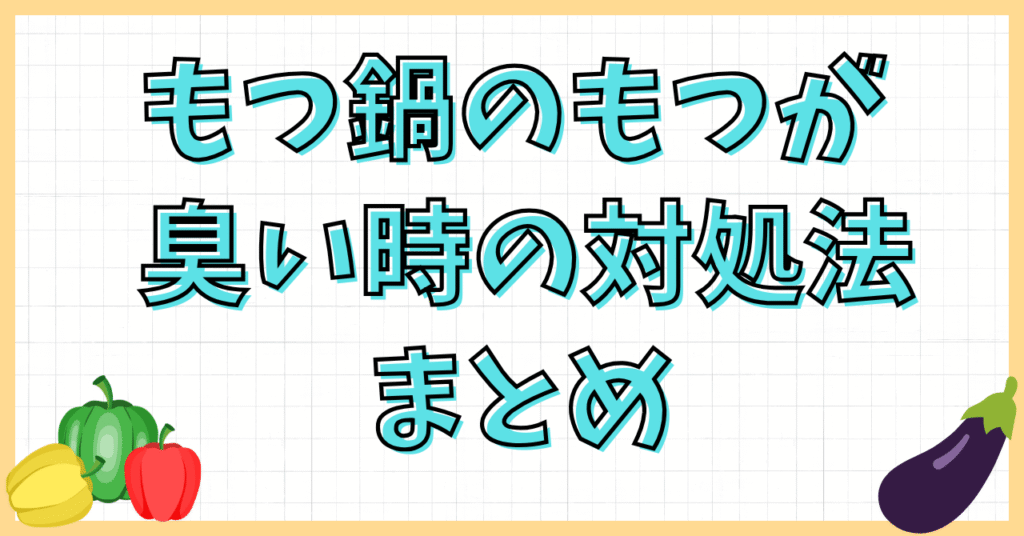
- もつの臭いの消し方の基本テクニック
- プロ直伝の美味しいスープの作り方
- にんにくは臭み消しに効果的?
- もつ鍋を食べた後の口臭ケア方法
- 2日目はアレンジで味わい尽くす!コショウ香るモツ鍋うどん
- まとめ:もつ鍋の「もつが臭い問題」解決
もつの臭いの消し方の基本テクニック
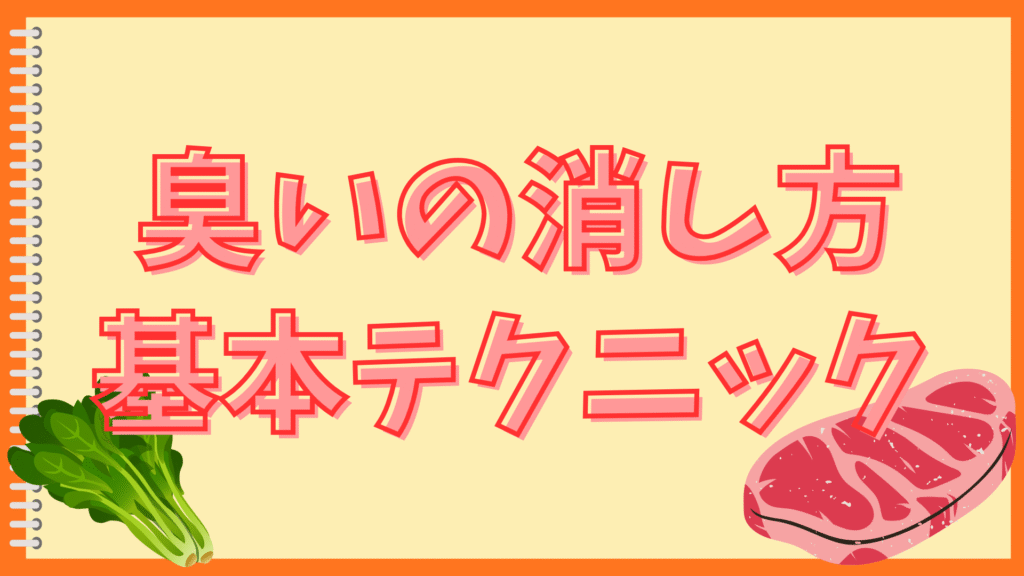
もつの臭みを効果的に取り除くためには、いくつかの方法を組み合わせることが鍵となります。
ここでは、家庭で簡単に実践できる基本的な下処理のテクニックを、手順を追って解説します。
これらの方法を丁寧に行うことで、もつの臭いを格段に抑えることが可能です。
1. 塩や粉類を使った洗浄
まず、もつに付着したぬめりや表面の汚れを物理的に取り除く作業から始めます。
- 塩もみボウルにもつを入れ、粗塩をたっぷりと振りかけて、力強く揉み込みます。塩の粒子が研磨剤の役割を果たし、ぬめりを絡め取ってくれます。また、浸透圧によってもつから余分な水分と一緒に臭みが出てくる効果も期待できます。全体をしっかりと揉み込んだら、流水で塩と汚れを完全に洗い流してください。
- 小麦粉・片栗粉塩もみの後、さらに臭いを取り除きたい場合におすすめなのが、小麦粉や片栗粉を使う方法です。水気を切ったもつに粉をまぶして揉み込むと、粉の細かい粒子が、塩だけでは落としきれなかった細かな汚れや臭いの元を強力に吸着してくれます。粉が灰色っぽくなったら、それが汚れを吸着した証拠です。その後、粉が残らないように、再度流水で徹底的に洗い流します。
2. 液体への漬け込み
洗浄の後は、液体に漬け込むことで、臭みの成分を中和させます。
- 牛乳牛乳に含まれるタンパク質の一種「カゼイン」には、臭い成分を吸着する働きがあります。もつが浸るくらいの牛乳に30分〜1時間ほど漬け込むと、驚くほど臭みが和らぎます。漬け込んだ後の牛乳は臭みが移っているので、しっかりと洗い流してから次の工程に進みましょう。
- 日本酒・料理酒アルコールにも臭みを揮発させたり、マスキングしたりする効果があります。日本酒や料理酒に30分ほど漬け込むのも有効な方法です。
3. 下茹で(茹でこぼし)
洗浄と漬け込みの仕上げとして、下茹でを行います。これは、残った臭みを熱で飛ばし、余分な脂を落とすための重要な工程です。
- 鍋にたっぷりのお湯を沸かし、ネギの青い部分や生姜のスライスなど、香味野菜と一緒にもつを入れます。
- 再沸騰してから5分(生もつの場合は10分)ほど茹で、ザルにあげてお湯を捨てます。このとき、茹で汁には臭みやアクが大量に出ているので、再利用はしません。
- ザルにあげたもつをもう一度流水で洗い、表面のアクなどをきれいに落とせば下処理は完了です。
- 一度で臭みが取りきれない場合は、この下茹での工程を2〜3回繰り返すと、より効果的です。ただし、長時間茹ですぎるともつが硬くなり、旨味まで抜けてしまうので注意が必要です。
プロ直伝の美味しいスープの作り方
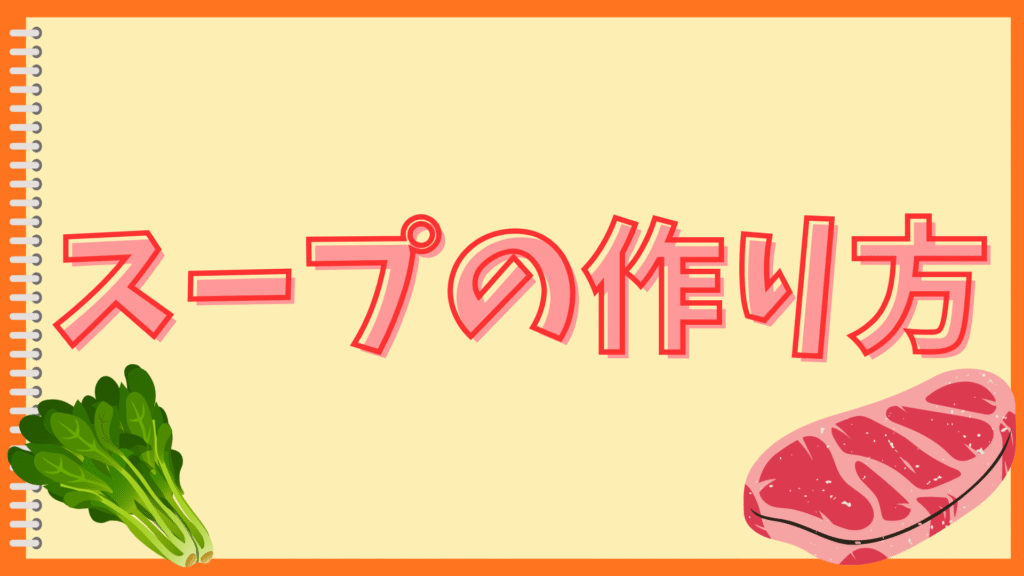
丁寧な下処理を施しても、もつの風味は独特です。
そこで、スープの味付けを工夫することで、残ったわずかな臭いをマスキングし、全体の味わいをさらに引き上げることができます。
ここでは、もつ鍋の定番である「醤油」「味噌」「塩」の基本スープと、出来上がった鍋がもし臭かった場合のリカバリー術を紹介します。
いずれのスープも味の基本はおいしいお水からです。【PREMIUM WATER】でおいしいスープを作りましょう。
基本の醤油スープ
もつ鍋の王道である醤油スープは、甘辛いバランスが食欲をそそります。カツオや昆布でとった和風だしをベースにすると、より深みのある味わいになります。
- 黄金比(3〜4人分)
- 水または和風だし:1000ml
- 醤油:80〜100ml
- みりん:50ml
- 料理酒:50ml
- 砂糖:大さじ1
- 鶏ガラスープの素:大さじ1
- (お好みで)にんにく、しょうがのすりおろし
コク旨の味噌スープ
濃厚でコク深い味噌スープは、特に寒い季節に体を温めてくれます。複数の味噌をブレンドすると、より複雑で奥行きのある味に仕上がります。
- 黄金比(3〜4人分)
- 水または和風だし:800ml
- 味噌:80〜100g
- 醤油:大さじ1
- みりん:大さじ2
- ごま油:大さじ1
- (お好みで)豆板醤、コチュジャン
味噌は煮立たせると風味が飛んでしまうため、他の調味料と具材を煮込んだ後、火を弱めてから溶き入れるのが美味しく作るコツです。
あっさり塩スープ
素材の味をストレートに楽しみたいなら、塩スープがおすすめです。ごまかしが効かない分、良質な鶏ガラスープや昆布だしを使うことが美味しさの鍵となります。
- 黄金比(3〜4人分)
- 水または鶏ガラスープ:1000ml
- 塩:小さじ2
- 薄口醤油:小さじ1
- (お好みで)柚子胡椒
もし鍋が臭くなってしまったら
調理後に臭みが気になる場合は、以下の方法でリカバリーを試みてください。
- 料理酒を追加する大さじ1〜2杯の料理酒を加え、1〜2分煮立たせてアルコールを飛ばします。アルコールが蒸発する際に、臭み成分も一緒に飛ばしてくれます。
- 香味野菜を増やすすりおろした生姜やにんにく、あるいは刻んだネギを追加します。香味野菜の強い香りが、もつの臭いを効果的にカバーしてくれます。
- 味付けを濃くする醤油や味噌を少し追加して、味を濃いめに調整します。調味料の風味が強まることで、臭いが感じにくくなります。
にんにくは臭み消しに効果的?
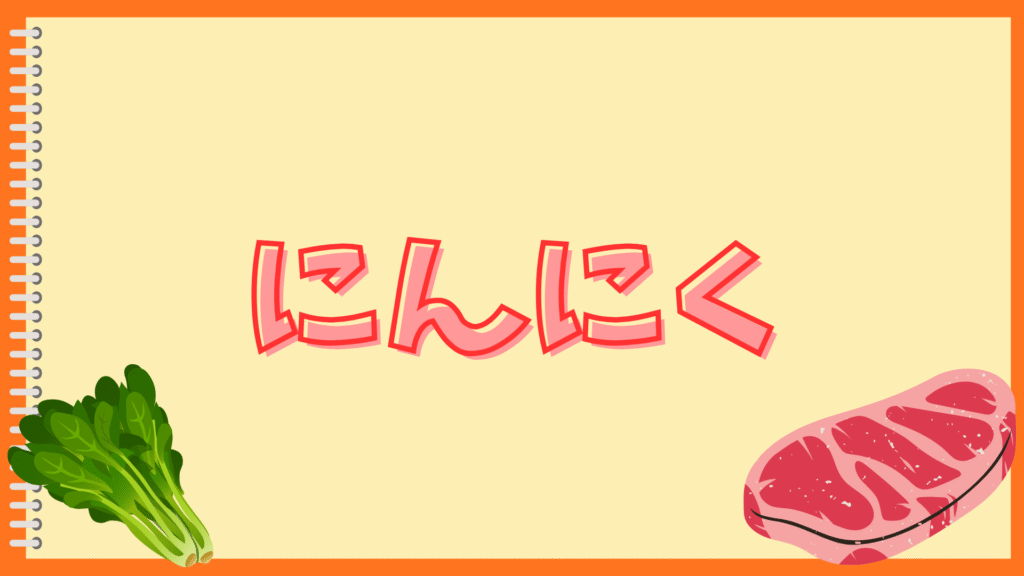
もつ鍋に欠かせない名脇役といえば、にんにくです。
このにんにくは、ただ単に風味を良くするだけでなく、もつの臭みを消す上でも非常に効果的な役割を果たします。
にんにく特有の強い香りの元である「アリシン」という成分には、他の食材の臭いをマスキング(覆い隠す)する強力な効果があります。
そのため、もつの独特な風味を和らげ、食欲をそそる香ばしい香りに変えてくれるのです。
ただし、にんにくを効果的に使うには、入れる量やタイミングを工夫することが大切です。
にんにくを入れるタイミング
- 調理の最初に鍋に油を熱し、スライスしたにんにくを弱火でじっくり炒めて香りを引き出してから、もつや他の具材を調理する方法です。油ににんにくの香りがしっかりと移るため、鍋全体に均一な風味が広がります。
- 煮込みの段階でスープと具材を煮込むタイミングで、すりおろしたにんにくやスライスにんにくを加える、最も一般的な方法です。スープににんにくの旨味と香りが溶け込み、味に深みを与えます。
- 仕上げに出来上がったもつ鍋を取り分けた器に、生のまま薄切りにしたにんにくをトッピングする方法です。加熱されたにんにくとはまた違う、フレッシュで刺激的な風味とシャキシャキとした食感を楽しむことができます。
使用量の注意点
にんにくは強力な効果を持つ一方で、入れすぎてしまうと、もつやスープの繊細な旨味がかき消されてしまう可能性があります。
また、翌日の口臭の原因にもなりやすいため、3〜4人前の鍋に対して、2〜3片程度を目安に、お好みで調整するのがよいでしょう。
にんにくは、もつ鍋の臭み対策における心強い味方ですが、全体のバランスを考えながら上手に活用することが、美味しさを最大限に引き出すコツです。
もつ鍋を食べた後の口臭ケア方法

美味しいもつ鍋を心ゆくまで楽しんだ後、少し気になるのが食後の口臭です。
もつ鍋による口臭は、もつ自体の風味に加え、にんにくやニラといった香りの強い香味野菜が主な原因となります。
せっかくの楽しい食事の思い出を台無しにしないためにも、適切なケア方法を知っておくと安心です。
食前・食中の対策
- 牛乳やヨーグルトを摂る食事の30分前くらいに牛乳や乳製品を摂っておくと、乳脂肪が胃の粘膜をコーティングし、臭い成分の吸収を和らげてくれる効果が期待できます。前述の通り、牛乳はもつの下処理にも使われるほど臭いを吸着する力が強いのです。
食後の対策
- 緑茶を飲む緑茶に含まれるカテキンには、強力な消臭・殺菌作用があります。にんにくの臭いの元であるアリシンと結合して臭いを抑える働きがあるため、食中や食後に緑茶を飲むのは非常に効果的です。
- リンゴを食べる食後のデザートにリンゴを食べるのもおすすめです。リンゴに含まれるポリフェノールや酵素が、口内に残った臭い成分を分解してくれます。皮ごと食べるとより効果が高いとされています。
- 丁寧なオーラルケア最も基本的かつ重要なのが、食後の歯磨きです。歯と歯の間だけでなく、臭い成分が付着しやすい舌の上(舌苔)も、舌ブラシなどを使って優しく清掃すると、口臭を大幅に軽減できます。マウスウォッシュの併用も効果的です。
これらの対策を組み合わせることで、もつ鍋を食べた後の口臭を気にすることなく、食事の余韻を楽しむことができます。
2日目はアレンジで味わい尽くす!コショウ香るモツ鍋うどん
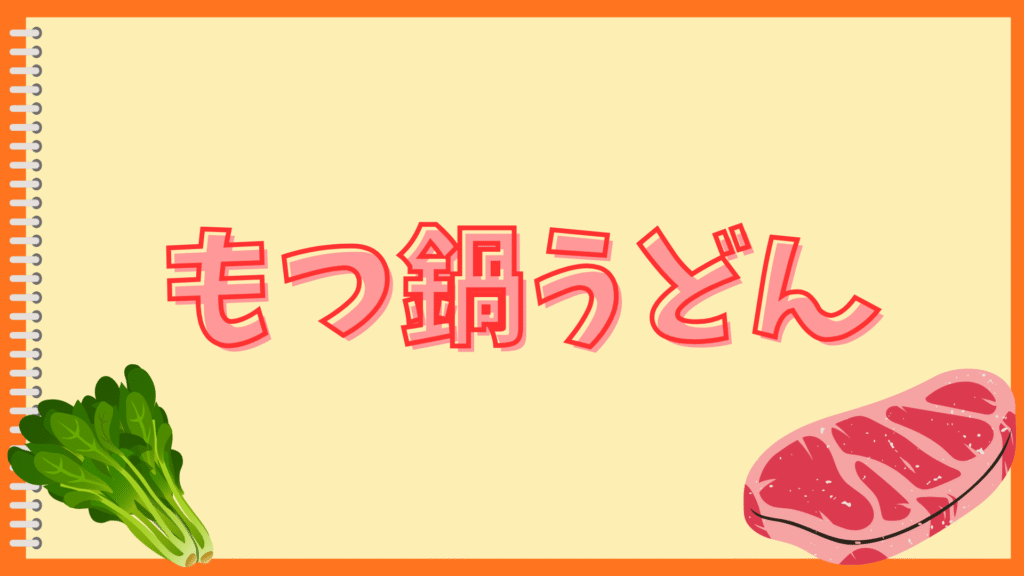
この記事では、もつ鍋の臭いの原因と家庭でできる対策の基本を解説してきました。
下処理で臭いを取り除いてつくった美味しいもつ鍋を、最後の一滴まで楽しむためには、スープまで飲み干すのがお決まりです。ところがスープまではお腹に入らない、なんてこともありますよね。
そんな時は無理をせずに残ったスープを冷蔵庫で保管しておきましょう。季節にもよりますが、多少風味は落ちるものの2~3日程度なら保管しておくことができます。
残ったスープは以下の記事ように別料理にアレンジして、美味しく生まれ変わらせることができます。詳しくは、当ブログ【コショウ香るモツ鍋うどん】をご参照ください。
ぜひ合わせてご覧いただき、あなたの「おうちもつ鍋」をさらにレベルアップさせてみてください。
まとめ:もつ鍋の「もつが臭い問題」解決
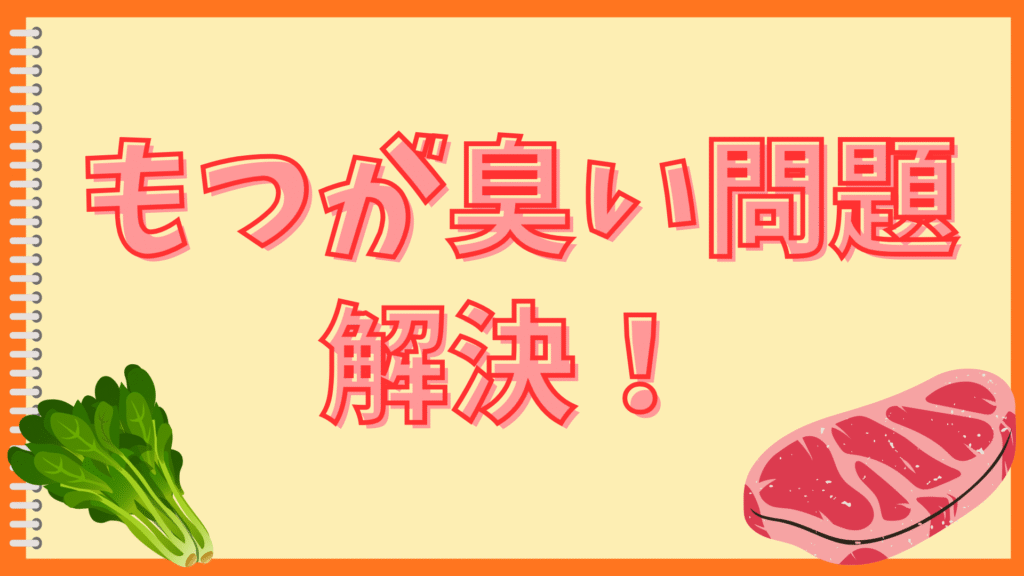
- もつ鍋が臭い主な原因はもつ自体にある
- 一般的に牛もつは豚もつより臭みが少ない
- もつ鍋には小腸や大腸がよく使われる
- 部位によって臭いの強さや食感が異なる
- もつは傷みやすく鮮度が落ちると臭くなる
- 購入後は冷蔵で1〜2日以内に使い切る
- 家庭での失敗は下処理不足がほとんど
- ボイル済みのもつでも再度の下処理は必要
- 塩もみでぬめりと臭いの元を取り除く
- 小麦粉は汚れや臭いを強力に吸着する
- 牛乳に漬けると臭み成分が中和される
- 下茹では香味野菜と一緒に行うと効果的
- スープの味付けを工夫することでも臭みは和らぐ
- にんにくは臭み消しと風味付けに役立つ
- 食後の口臭ケアも忘れずに行う