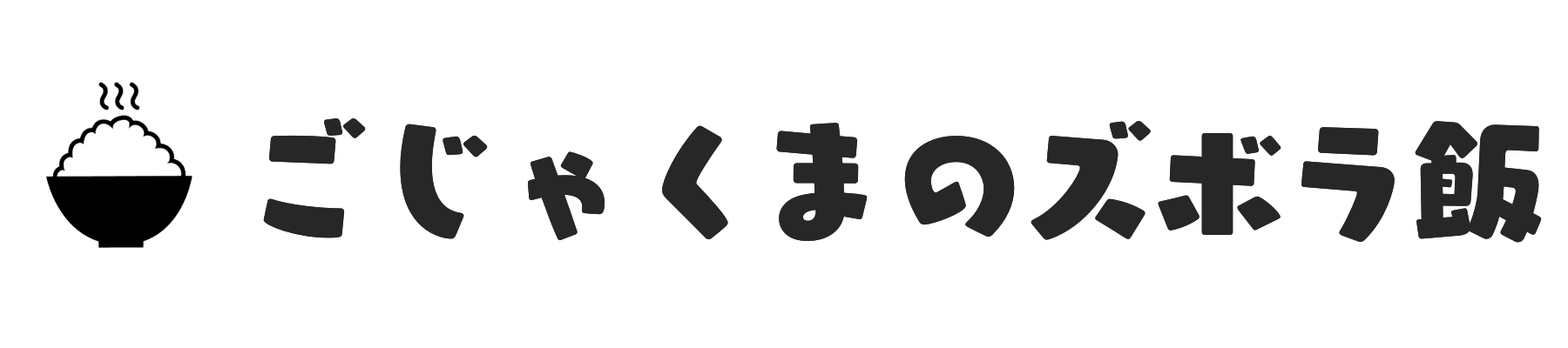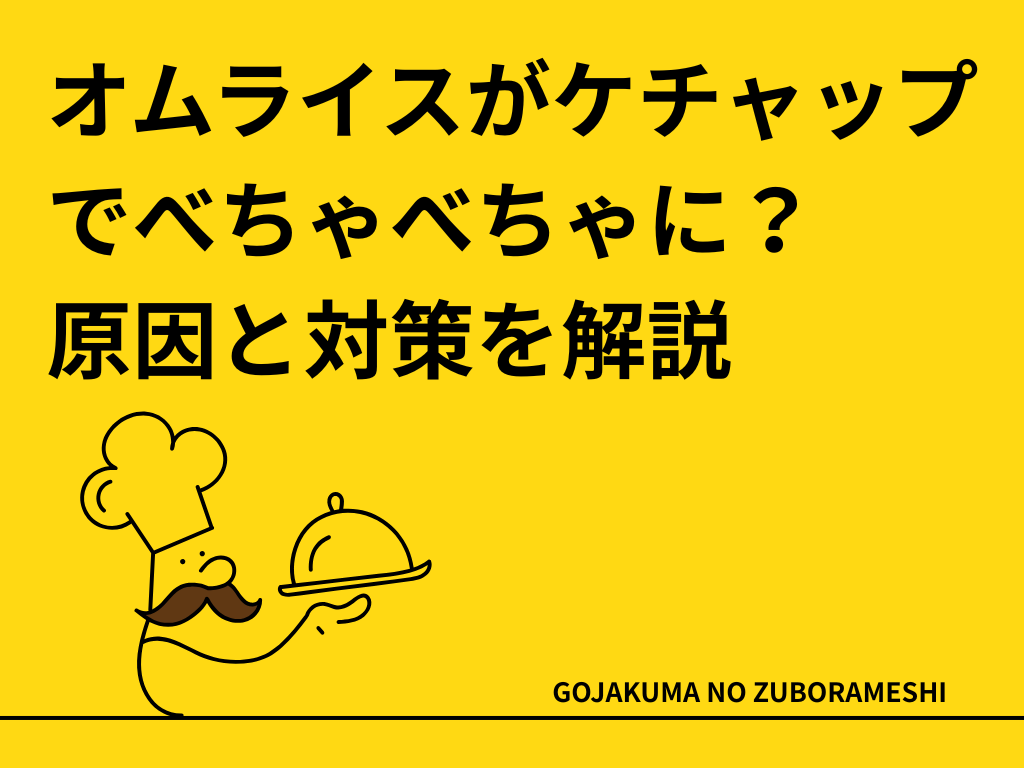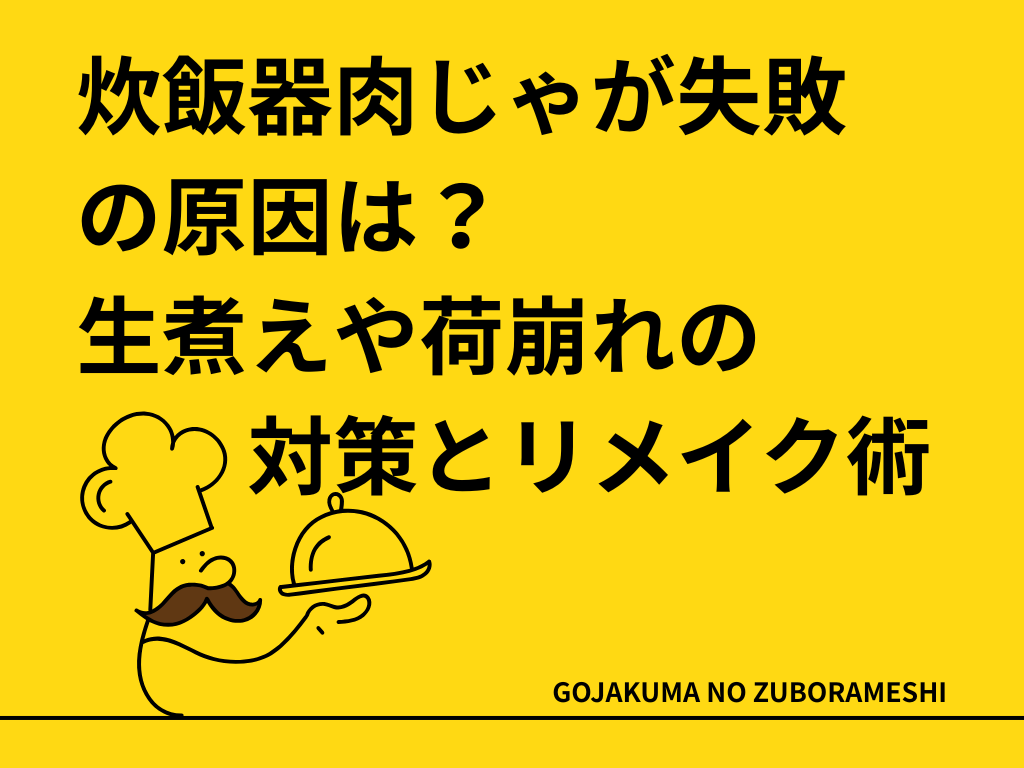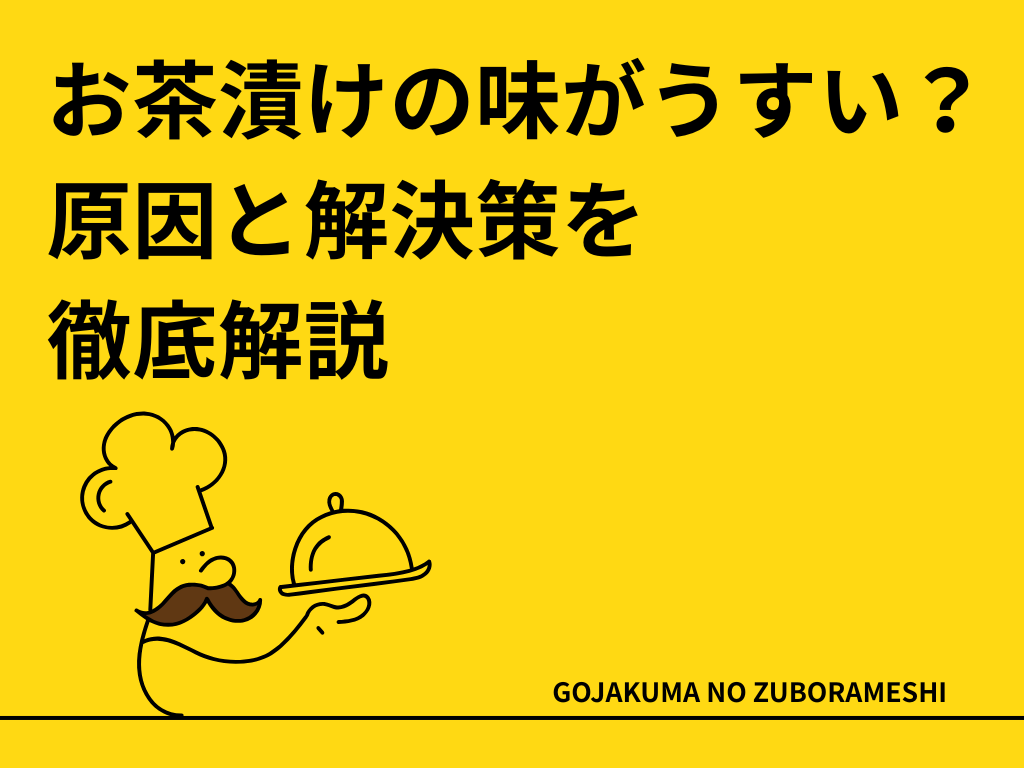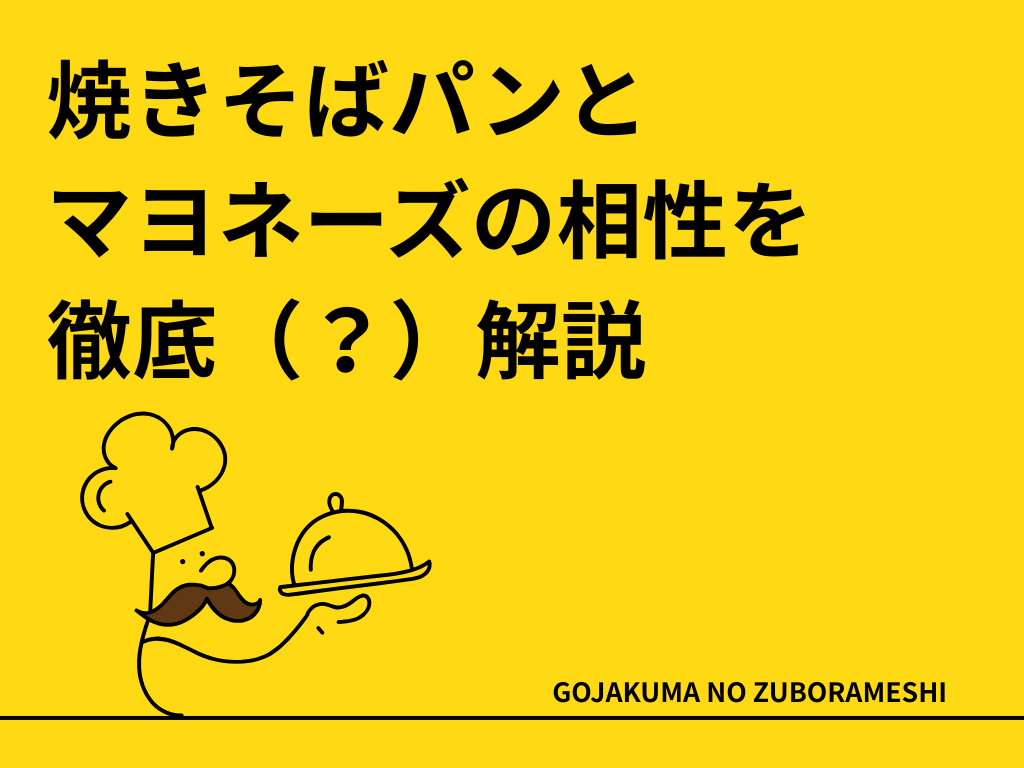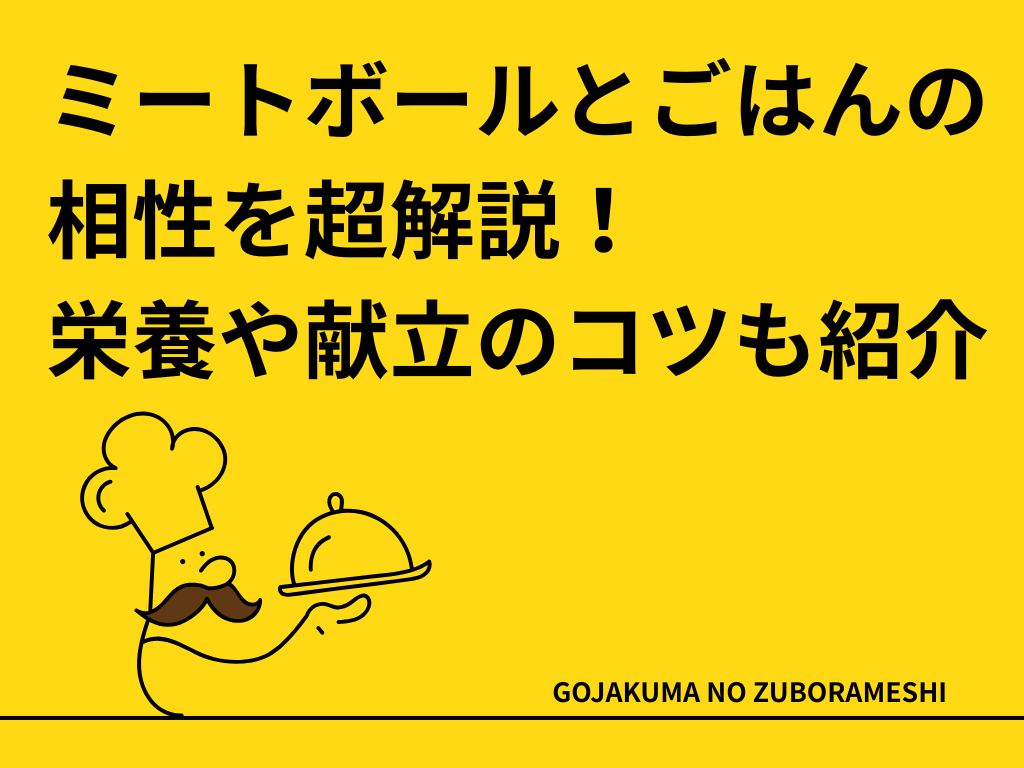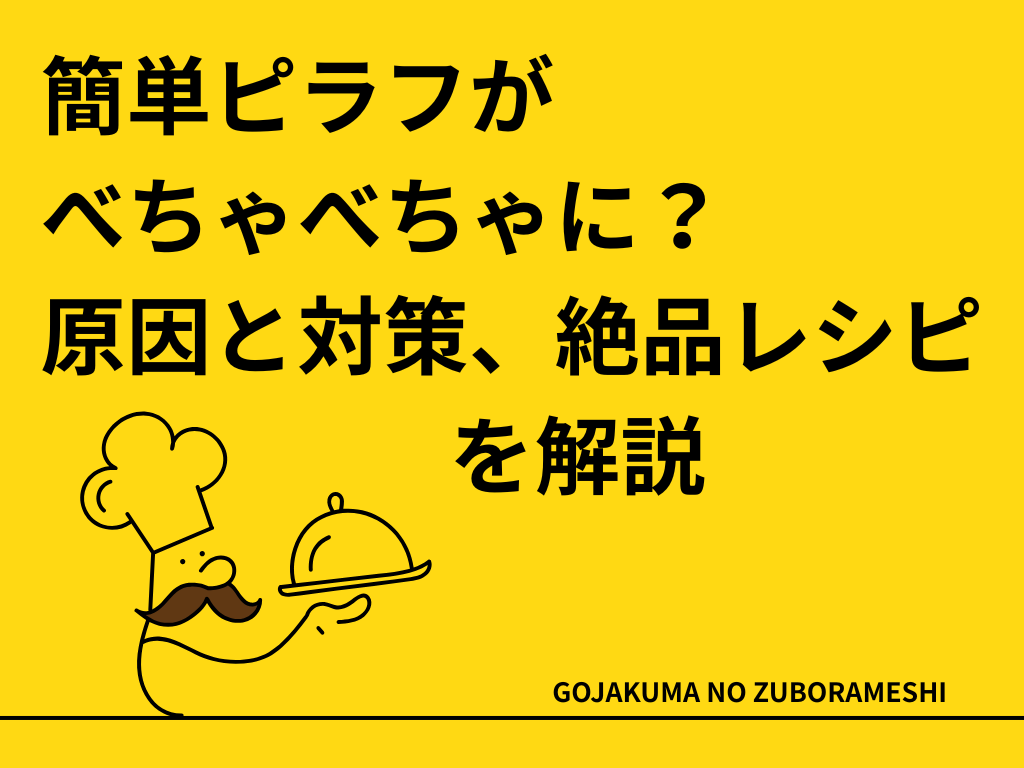大根が辛いのはなぜ?理由と対処法、栄養まで解説
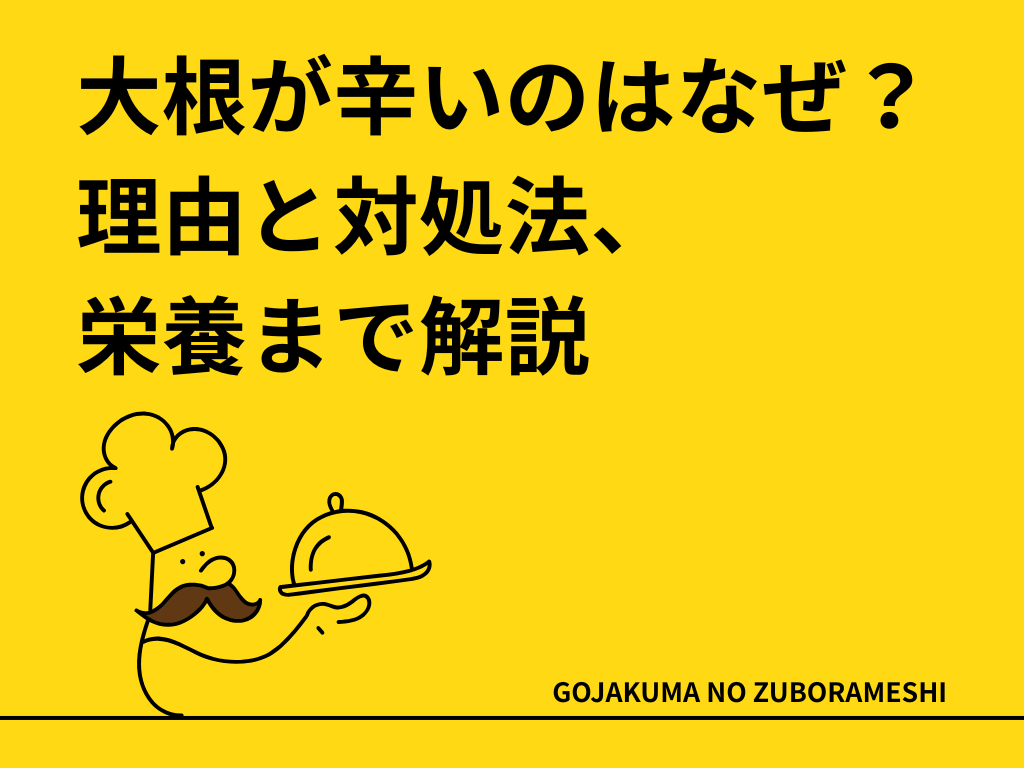
大根を食べた時、予想以上の辛さに驚いた経験はありませんか。特に「大根 辛い」と調べている方は、その原因やおいしく食べるための具体的な対処法を探していることと思います。
大根は、首(葉に近い方)と尻尾(先端)のどちらが辛いのか、そもそもなぜ辛いのか、理由を知ることで調理法が変わってきます。
この記事では、大根の辛味を上手に消す方法から、辛味成分が持つ栄養素、さらには効果的な食べ方や食べ合わせの知識まで、幅広く解説します。
また、煮物を作る際の「下茹では必要ない?」という疑問や、大根が傷んで食べられない時のダメなサインの見分け方についても触れていきます。大根の辛味を理解し、上手に付き合うための一助となれば幸いです。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 大根が辛くなる理由と辛味が強い部位
- 辛味を抑えたり、消したりする具体的な調理法
- 辛味成分の栄養価と、栄養を活かす食べ方
- 調理の疑問や、傷んだ大根の見分け方
大根 辛い理由と辛味への対処法
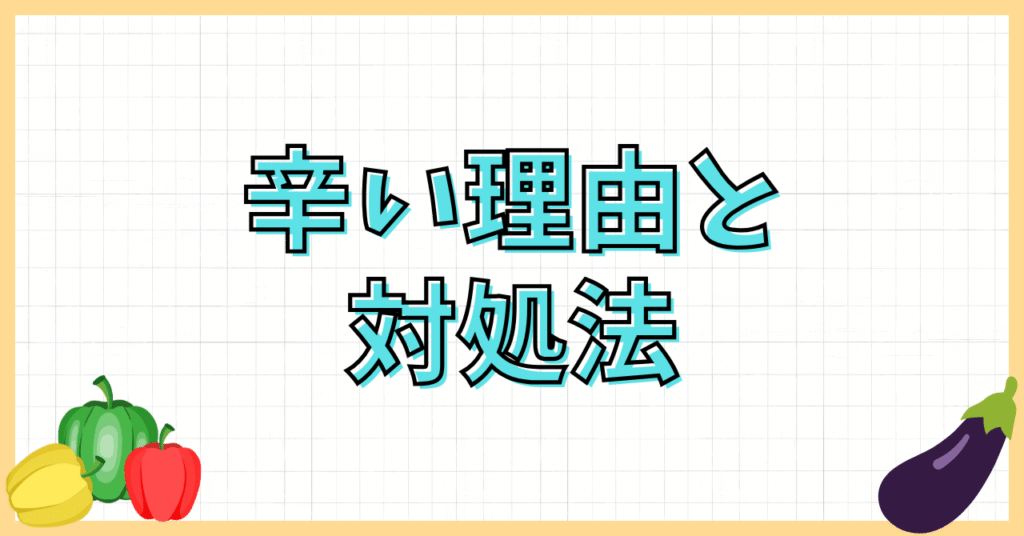
- 大根はなぜ辛いのか?成分を解説
- 大根の首と尻尾、辛いのはどっち?
- 辛すぎた場合の基本的な対処法
- 調理で大根の辛味を消す工夫
大根はなぜ辛いのか?成分を解説
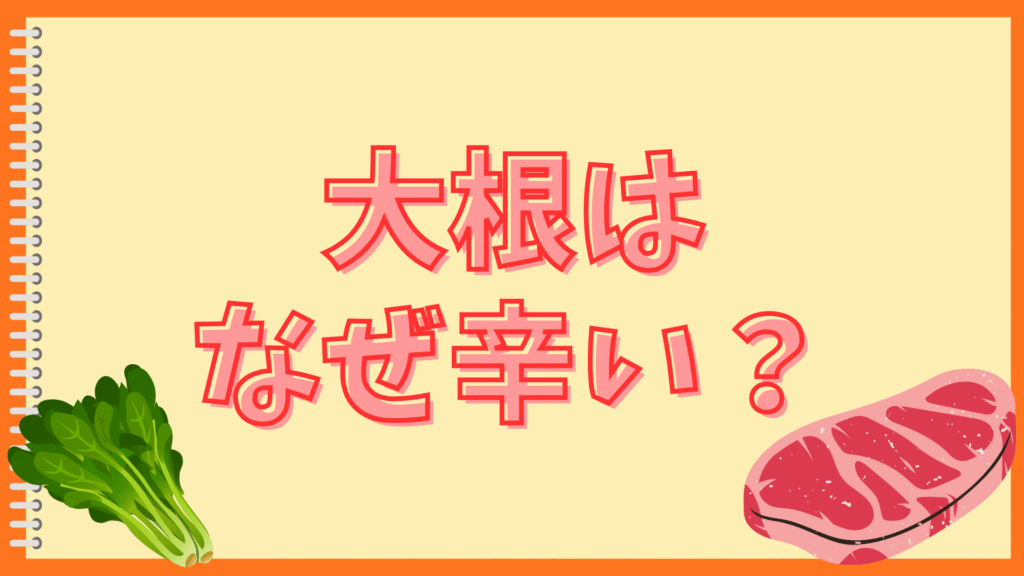
大根の辛味の正体は、「イソチオシアネート」という成分です。ただし、大根の細胞の中にもともとこの辛い成分が存在しているわけではありません。
大根の細胞には、「グルコシノレート」(辛味のもとになる物質)と、「ミロシナーゼ」(酵素)が別々の場所に存在しています。
大根を切ったり、すりおろしたりして細胞が壊れると、この二つが初めて混ざり合います。すると、化学反応が起きて「イソチオシアネート」(アリルイソチオシアネートとも呼ばれます)という辛味成分が生成されるのです。
これが、大根を生でかじるよりも、大根おろしにした方が強く辛味を感じる理由です。細胞が細かく壊されるほど、酵素の反応が活発になり、辛味成分が多く作られます。
また、この辛味成分は、害虫などから身を守るために備わった防御機能とも言われています。そのため、含まれる量には部位や季節によって差が生じます。
大根の首と尻尾、辛いのはどっち?
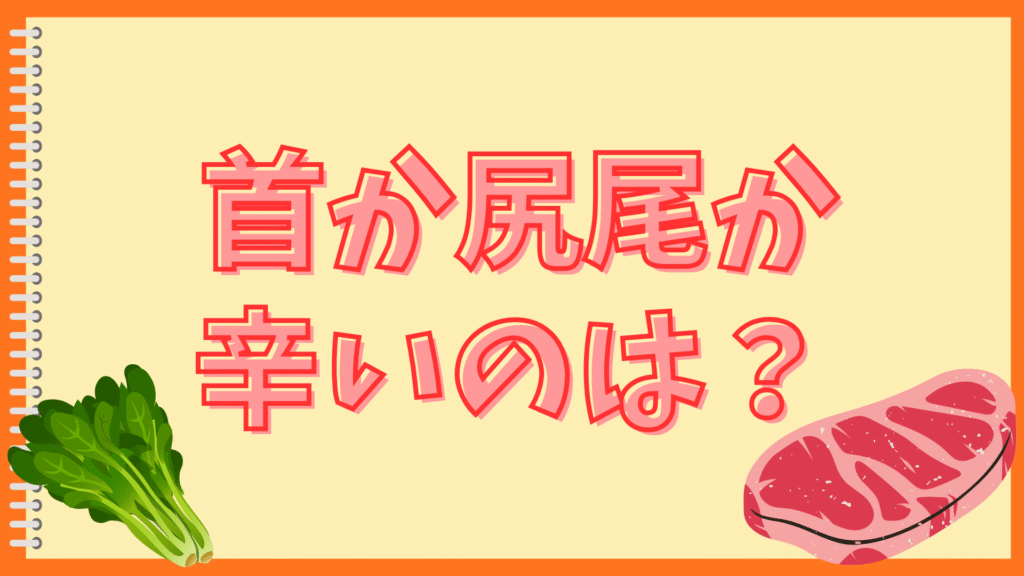
大根は、部位によって辛さが大きく異なります。
結論から言うと、辛味が強いのは「尻尾」、つまり先端に近い部分です。逆に、葉に近い「首」の部分は甘味が強くなります。
尻尾(先端)に行くほど辛味が強くなるのは、成長過程で細胞分裂が活発に行われる先端部分に、害虫を寄せ付けないための辛味成分(のもとになる物質)が多く蓄積されるためと考えられています。
一方、首(上部)は水分が多く、甘味を感じやすくなっています。真ん中の部分は、辛味と甘味のバランスが取れた部位です。
この部位による味の違いを理解しておくと、料理によって使い分けることができます。
| 大根の部位 | 味の特徴 | おすすめの料理 |
| 首(上部) | 甘味が強く、みずみずしい。硬め。 | サラダ、野菜スティック、大根おろし(甘口) |
| 真ん中 | 甘味と辛味のバランスが良い。柔らかい。 | 煮物(おでん、ふろふき大根)、ステーキ |
| 尻尾(下部) | 辛味が最も強い。水分が少なめ。 | 大根おろし(辛口)、漬物、炒め物、薬味 |
辛すぎた場合の基本的な対処法

大根をおろした後で「辛すぎた」と困った場合、最も手軽な対処法は「時間を置くこと」です。
前述の通り、大根の辛味成分であるアリルイソチオシアネートは、「揮発性(きはつせい)」という性質を持っています。これは、時間とともに空気中に蒸発していく性質のことです。
辛味は、すりおろしてから約5分後にピークに達すると言われています。その後、時間経過とともに徐々に辛味が抜けていきます。もし辛味が強すぎると感じた場合は、ラップなどをかけずにそのまま30分から1時間ほど放置してみてください。
ただし、この方法には注意点もあります。長時間放置しすぎると、大根の水分も一緒に蒸発してしまい、食感がパサパサと悪くなる可能性があります。また、ビタミンCなど一部の栄養素も時間とともに失われる可能性が指摘されています。
味と食感のバランスを見ながら、放置時間を調整することが望ましいです。
調理で大根の辛味を消す工夫

時間を置くだけでなく、調理の過程で辛味を意図的に抑える方法もいくつか存在します。
加熱処理を行う
辛味成分イソチオシアネートは熱に弱い性質を持っています。そのため、加熱調理は辛味を消す最も効果的な方法の一つです。
もし辛い大根おろしが出来てしまった場合、耐熱容器に入れ、ラップをかけずに電子レンジ(600W)で15秒から30秒ほど加熱してみてください。
加熱しすぎると風味も飛んでしまうため、短い時間から試して味見をしながら調整するのがおすすめです。
もちろん、炒め物や煮物、味噌汁の具にするなど、最初から加熱する料理に使えば、辛味はほとんど感じなくなります。
水にさらす、または酢やレモンを加える
大根おろしを水にさらすと、辛味成分が水に溶け出して辛味が和らぎます。
ただし、この方法はビタミンCなどの水溶性の栄養素も一緒に流れ出てしまうデメリットがあります。
また、辛味成分は酸によっても緩和されるため、大根おろしに少量の酢やレモン果汁を加えるのも一つの手です。
切り方や皮の剥き方を工夫する
辛味成分は、皮に近い外側の部分に多く含まれています。したがって、皮をいつもより厚めに(約3mm程度)剥くことで、辛味を強く感じる部分を取り除くことができます。
また、大根の繊維は縦方向に走っています。この繊維に沿って(縦方向に)切ったり、おろしたりすると、細胞があまり壊れにくくなります。
細胞の破壊が抑えられると、辛味成分の生成量も少なくなるため、辛味がマイルドになります。逆に、繊維を断ち切るように(横方向や円を描くように)おろすと、辛味が強くなります。
辛くない大根おろしを作りたい場合は、「葉に近い甘い部分を使い」「皮を厚めに剥き」「繊維に沿って縦に」「優しく粗めに」おろすのが良い、ということになります。
大根の「辛い」を活かす栄養と調理法
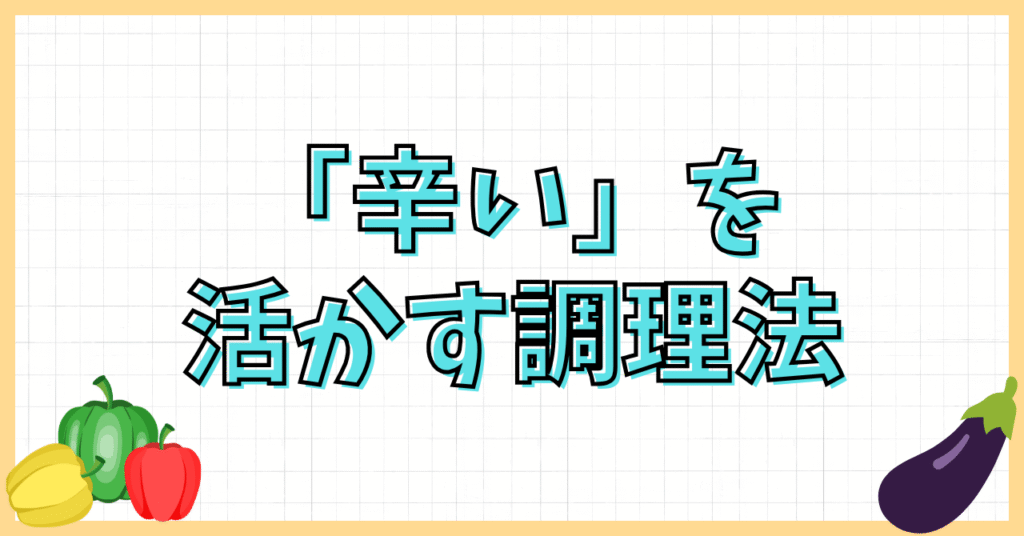
- 大根の辛味成分と主な栄養素
- 栄養を逃さない効果的な食べ方
- 意外と知らない大根の食べ合わせ
- 煮物の下茹では必要ない?
- 食べるのは危険!ダメなサインとは
- 大根が辛い時の知識まとめ
大根の辛味成分と主な栄養素
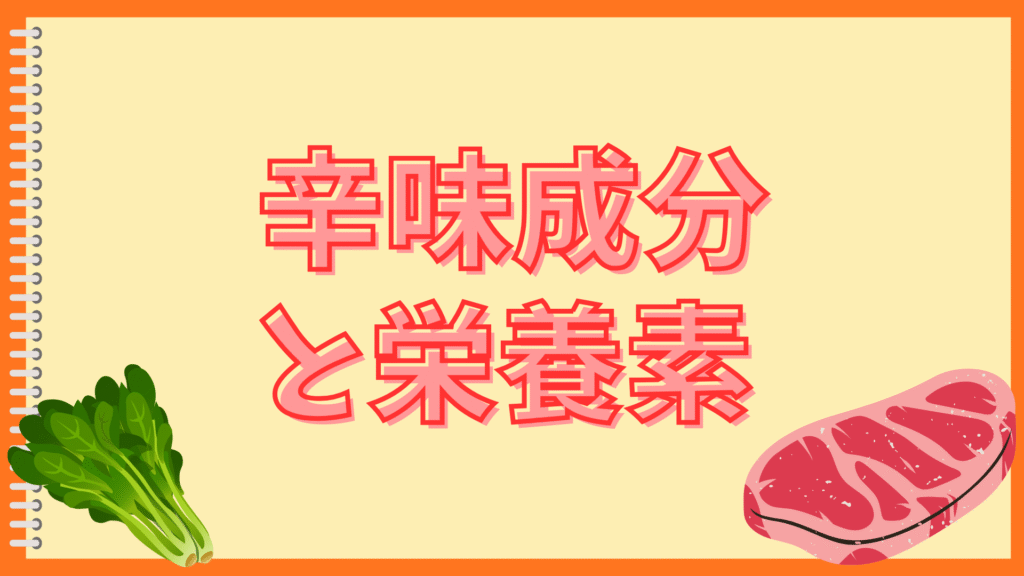
大根が辛い原因となる成分「イソチオシアネート」ですが、実は体に良い影響を与える成分としても注目されています。
イソチオシアネートには、強い抗酸化作用や殺菌作用があると言われています。抗酸化作用は、老化の原因とされる活性酸素の働きを抑えるのに役立ちます。
また、殺菌作用は食中毒の原因となる菌への効果も期待されています。焼き魚に大根おろしを添えるのは、味をさっぱりさせるだけでなく、魚の焦げに含まれる発がん性物質の働きを抑える効果も期待できる、理にかなった食べ合わせです。
もちろん、大根には辛味成分以外の栄養素も含まれています。
代表的なものは、デンプンの消化を助ける「アミラーゼ(ジアスターゼ)」などの消化酵素です。胃もたれや胸やけの防止に役立つとされ、古くから消化を助ける食材として知られています。
ただし、これらの消化酵素は熱に弱いため、効果を期待するなら生で食べる必要があります。
他にも、美肌効果や免疫力向上に関わる「ビタミンC」、体内の余分なナトリウムを排出する「カリウム」なども含まれています。
葉の栄養素
もし葉付きの大根を手に入れた場合、葉の部分は捨てずに活用することをおすすめします。
大根の葉は、根の部分には少ない「βカロテン」や「ビタミンK」、「カルシウム」などを豊富に含む緑黄色野菜です。
栄養を逃さない効果的な食べ方
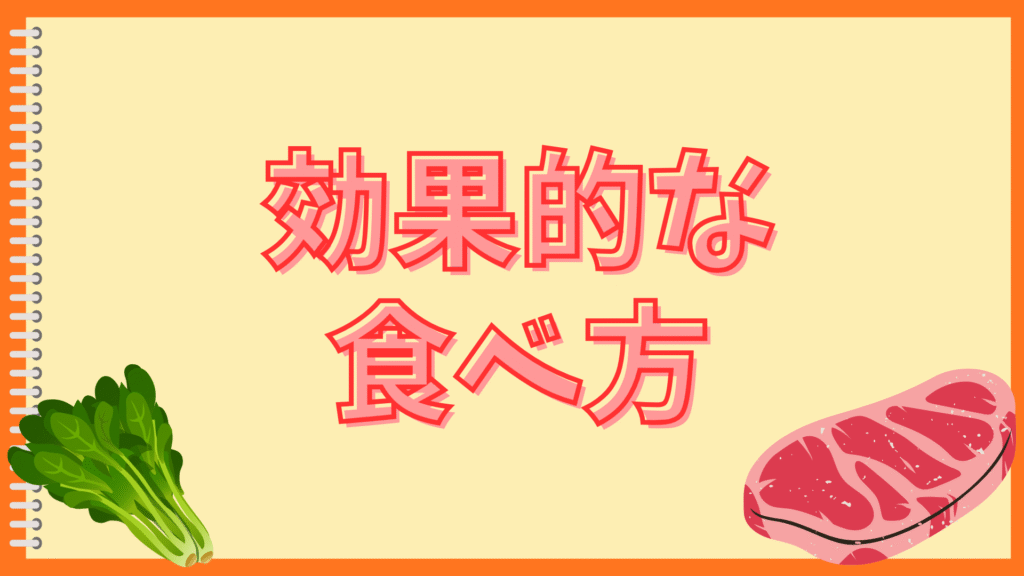
大根に含まれる栄養素を効率よく摂取するためには、いくつかのポイントがあります。
第一に、「生で食べる」ことです。
前述の通り、大根に含まれる消化酵素(アミラーゼなど)やビタミンCは熱に弱い性質を持っています。そのため、これらの栄養素をしっかり摂りたい場合は、加熱せずに大根おろしやサラダ、野菜スティックなどで食べるのが最適です。
第二に、「皮ごと食べる」ことです。
大根の皮の近くには、中心部分よりも多くのビタミンCが含まれていると言われています。皮の食感が気にならない場合は、よく洗って皮ごと調理する(特に大根おろしや漬物、炒め物など)と、栄養を無駄なく摂取できます。
第三に、「葉も食べる」ことです。
βカロテンは脂溶性(油に溶けやすい性質)のため、葉をごま油などで炒めたり、油揚げと一緒に煮たりすると吸収率が上がります。
栄養素を効率よく摂取する食べ方といえば生食ですが、ごじゃくま家では、大根サラダが定番です。【ザクザク食べられる! 簡単ドレッシングの大根サラダ】に詳しい作り方(といっても簡単ですが…)を紹介していますので、のぞいてみてください。
意外と知らない大根の食べ合わせ
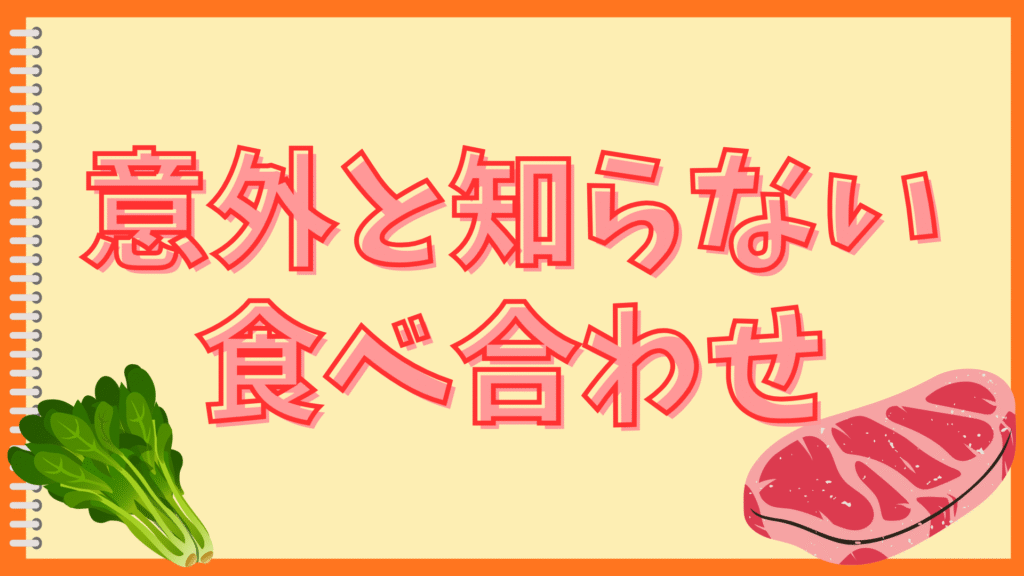
大根は様々な食材と組み合わせて使われますが、栄養素の観点から見ると、良い組み合わせと、少し注意が必要な組み合わせがあります。
良い食べ合わせ
胃腸の働きを助ける消化酵素を活かすため、やまいも(同じくアミラーゼを含む)や納豆(ネバネバ成分が胃粘膜を保護)などと組み合わせるのは良いとされています。
また、豚肉や鶏肉などタンパク質が豊富な食材と合わせることで、大根の消化酵素がタンパク質の分解を助けるとも言われています。
注意が必要な食べ合わせ
一般的に注意が必要とされる組み合わせに、「にんじん」や「きゅうり」があります。これらに含まれる「アスコルビナーゼ」という酵素が、大根のビタミンCを壊してしまう可能性があるためです。
ただし、このアスコルビナーゼは「熱」と「酸」に弱い性質を持っています。そのため、生のまま合わせる場合でも、酢を使ったドレッシングやマリネにすれば、酵素の働きを抑えられます。
また、煮物や味噌汁のように一緒に加熱調理する場合は、気にする必要はありません。
もう一つ、「しらす」との組み合わせ(しらすおろし)も、栄養の観点で指摘されることがあります。
大根に含まれる酵素(リジンインヒビター)が、しらすに含まれる必須アミノ酸「リジン」の吸収を妨げるという説があるためです。
これも、お酢やポン酢など酸性のものを一緒にかけることで、酵素の働きを弱めることができるとされています。
煮物の下茹では必要ない?
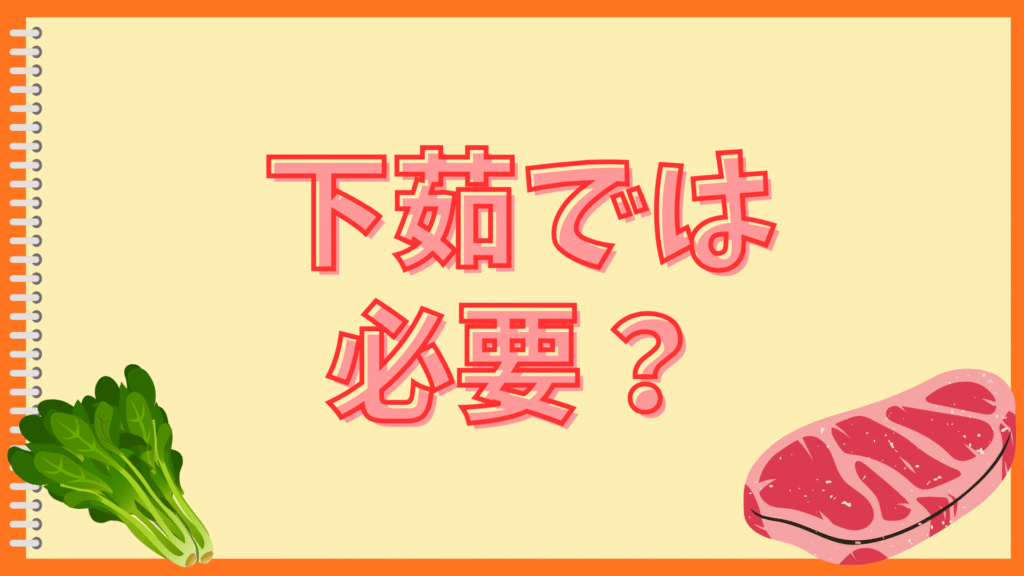
おでんやふろふき大根、煮物を作る際、レシピに「大根を下茹でする」と書かれていることがよくあります。この工程は本当に必要なのでしょうか。
これには二つの考え方があります。
一つは「必要ない」という考え方です。
昔の大根は苦味やえぐみが強かったため、米のとぎ汁などで下茹でしてアク抜きをする必要がありました。しかし、現在の品種改良された大根は苦味が少なく、そのまま煮ても十分おいしく食べられる、というものです。
もう一つは「下茹でした方が良い」という考え方です。
下茹でをすることで、わずかな辛味やえぐみが抜け、大根本来の甘味が引き立ちます。
また、米のとぎ汁(または生米や片栗粉を少し入れた水)で下茹でをすると、米のでんぷんが大根のアクを吸着してくれると同時に、大根の細胞壁が柔らかくなり、味が染み込みやすくなる効果が期待できます。
どちらが正しいというわけではなく、料理によって使い分けるのが現実的です。
時間がない時の簡単な煮物であれば下茹でを省略しても問題ありませんが、おでんやふろふき大根のように、大根にじっくりと味を染み込ませたい料理の場合は、下茹でというひと手間を加える価値は十分にあると考えられます。
食べるのは危険!ダメなサインとは
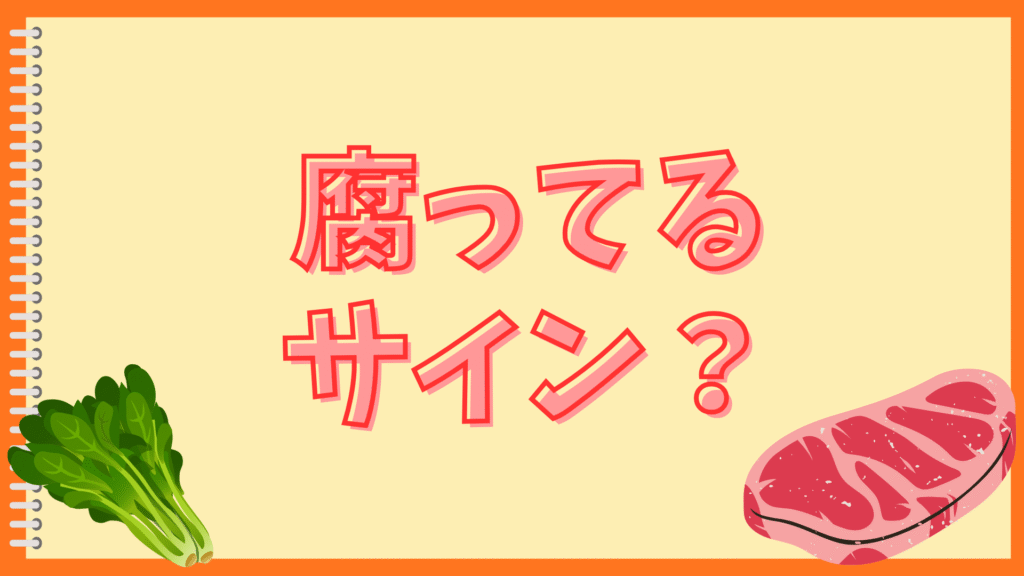
大根は比較的日持ちする野菜ですが、保存状態が悪いと腐敗してしまいます。
食べると健康を害する可能性があるため、傷んだ大根のサインを知っておくことは大切です。
生の状態での見分け方
- 見た目: 表面や切り口に黒カビや白カビ(綿のようなもの)が生えている。全体が茶色っぽく変色している。
- におい: 明らかに酸っぱいにおいや、腐敗したような異臭がする。
- 感触: 触るとぬめりがある。どろっとした汁が出ている。部分的に、または全体が崩れるほど柔らかくなっている。
なお、単に水分が抜けて柔らかくなったり、皮にしわが寄ったりしているだけの場合は、傷んでいるわけではありません。
異臭やぬめりがなければ、煮物や炒め物などで食べることが可能です。
調理後の注意点
調理済みの煮物なども、常温で長時間放置すると腐敗します。特に肉や魚介類と一緒に煮込んだ場合、「ウエルシュ菌」という食中毒の原因菌が増殖しやすい環境になります。
ウエルシュ菌は熱に強い性質を持つため、食べる直前に再加熱するだけでは防ぎきれないことがあります。
作り置きした煮物は、粗熱が取れたら速やかに冷蔵庫や冷凍庫で保存し、早めに食べきるようにしてください。
大根が辛い時の知識まとめ
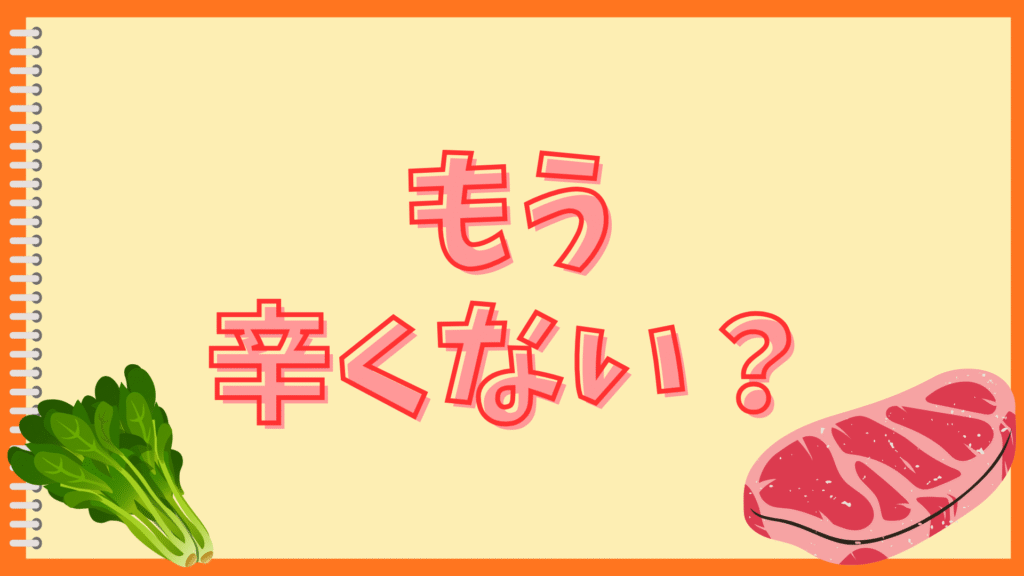
この記事で解説した「大根が辛い」に関する知識や対処法を、箇条書きでまとめます。
- 大根の辛味成分は「イソチオシアネート」
- 切ったりすりおろしたりして細胞が壊れると生成される
- 辛味は害虫から身を守るための成分とも言われる
- 辛いのは「尻尾(先端)」、甘いのは「首(葉に近い方)」
- 先端は薬味や漬物に、中央は煮物に、上部はサラダに向く
- 辛すぎる時の対処法は「30分ほど放置する」こと
- 辛味成分は揮発性(蒸発する性質)を持つため
- 辛味を消すには「加熱」が最も効果的
- 電子レンジでの短時間加熱も有効
- 皮を厚く(3mm目安)剥くと辛味が和らぐ
- 繊維に沿って(縦に)切る、またはおろすと辛味が抑えられる
- 辛味成分イソチオシアネートには抗酸化作用や殺菌作用が期待できる
- 大根には消化酵素(アミラーゼ)やビタミンCも含まれる
- 消化酵素やビタミンCは熱に弱いため「生食」が効率的
- 煮物の下茹では、味を染み込ませたい料理(おでん等)に有効
- 腐敗した大根はカビ、異臭、ぬめりで見分ける